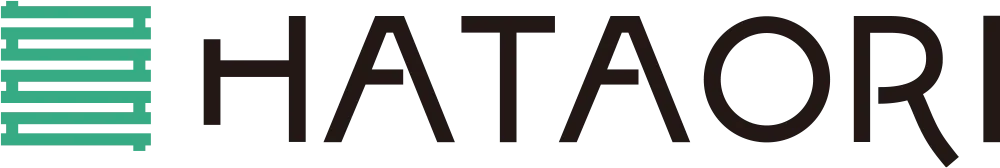Google検索アルゴリズムの“MUM(Multitask Unified Model)”とは?
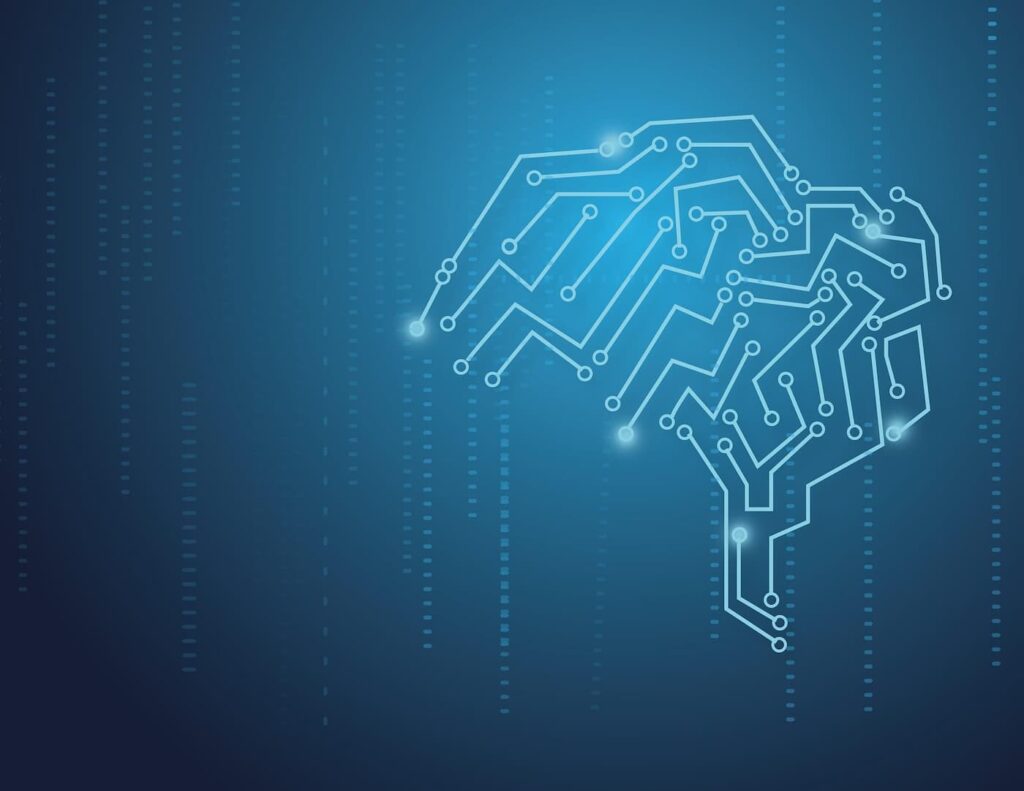
検索で調べごとをしていると、単語をいくつも打ち替えたり、複数のタブを行き来したりします。
人間なら「この状況なら、こう比較すれば早い」と勘で近道できますが、検索エンジンはその文脈を完全には読めませんでした。
そこで投入されたのがMUM(Multitask Unified Model)です。
画像やテキスト、複数言語にまたがる情報を横断し、複雑な質問に一歩踏み込んだ“導き”を目指します。
少し肩の力を抜いて、仕組みと実務の変え方を一緒に整理してみましょう。
目次
MUM(Multitask Unified Model)とは
MUMは、Googleが開発した検索用のAIモデルです。T5系のテキスト-to-テキスト技術を土台にしたマルチタスク・マルチモーダルの理解モデルを指します。
特徴は「一度にたくさんのことを理解できる」点にあり、言語をまたいだり、文章や画像など複数の情報形式を組み合わせて意味をつかめます。
目的は、少ない操作で複雑な課題を解くことを目的に、言語間の知識移転や画像等の手掛かりを併用して検索者の意図を補助します。
MUMの目的
従来の検索は、知りたいことがあっても「登山靴のおすすめ」→「秋に向いている登山靴」→「日本で買えるブランド」…とキーワードを何度も入れ替える必要がありました。
MUMはこうした複雑な調べものを、一度の検索でまとめて理解し、関連情報を橋渡しすることを狙っています。
マルチモーダルと多言語対応の要点
MUMの「マルチモーダル」とは、テキスト(文章)だけでなく、画像なども合わせて意味を読み取れることを指します。
たとえば「この写真の靴は冬山にも使える?」と画像をアップすると、テキスト情報と組み合わせて答えられる可能性が出てきます。
また「多言語対応」とは、英語や中国語など他の言語で信頼できる記事を、日本語の検索結果に役立てることです。
これにより、これまで日本語の情報が少なかったテーマでも、海外の知見を活用して検索結果を充実させられます。
情報探索の高度化と課題解決
MUMのゴールは「検索体験をよりスムーズにする」ことです。
ユーザーが大回りして複数ページを調べなくても、必要な情報のつながりをあらかじめ整理して見せる仕組みです。
言い換えると、MUMは検索エンジンを「ただの地図」から「旅のプランナー」に進化させようとしている、と考えると分かりやすいかもしれません。
BERTとの違いと補完関係
検索の高度化を語るとき、よく比較に挙がるのが「BERT」と「MUM」です。
両者は似たように思われがちですが、実は役割が異なります。BERTは検索に“読解力”を与えた存在であり、MUMはそれをさらに拡張して“総合アドバイザー”のような機能を果たします。
つまり置き換えではなく補完関係にあり、両者がそろうことで検索は大きく進化しました。
BERTの役割
BERTは2019年にGoogle検索に導入された仕組みで、文章を「単語単位」ではなく「文脈」として理解できるようにしたのが大きな特徴です。
たとえば「電車 カード」という検索をすると、従来は「電車カード」という商品ページが出てしまうことがありました。
しかしBERTは「電車に乗るためのカード=ICカード」という意味を読み取り、より適切な検索結果を提示できるようになりました。
つまりBERTは、検索に“読解力”を持たせたといえます。
参考サイト:
MUMで加わる能力拡張
MUMは、BERTが築いた文脈理解の力を土台に、さらに多言語や画像など複数形式の情報を組み合わせて処理できるようになっています。
たとえば「この登山靴の写真は富士山登山に適しているか?」と質問するとMUMは写真の特徴を理解し、さらに英語の記事や海外の登山レポートも参照しながら判断の助けとなる情報を提示できます。
つまりMUMは、単なる読解力にとどまらず、検索を“広く・深く”つなげる能力を備えています。
施策観点での実務的な違い
SEOにおいてBERT導入後は「検索意図をきちんと捉えた記事を書く」ことが重要視されるようになりました。
これは普遍的なもので変わりませんが、MUMの登場によって、サイトには「単発の答え」ではなく「比較や手順、根拠を体系的に整理した情報」が求められるようになっています。
BERTが検索の“読解力”を底上げし、MUMが“複雑な質問に総合的に案内する力”を与えた、と考えると違いが理解しやすいでしょう。
MUMとSGE・AI Overviewsとの関係
検索体験の変化を語るとき、MUMと並んでよく話題になるのが「SGE(Search Generative Experience)」や「AI Overviews」です。
名前が似ていて混同されがちですが、役割は違います。
MUMは検索の“理解する力”を底上げする技術であり、SGEやAI Overviewsはその理解をユーザーに“どう見せるか”という体験の部分を担います。
両者を切り分けて考えると、検索の進化がより分かりやすくなります。
体験レイヤーと能力レイヤーの切り分け
MUMは検索エンジンの内部で「複雑な質問を理解する」能力を強化します。
一方でSGEやAI Overviewsは、その理解結果を「要約」や「生成回答」といった形で画面に提示する仕組みです。
たとえば料理レシピを調べるとき、MUMが材料や調理手順の関係を理解し、SGEがそれを要約した回答としてユーザーに提示する、といった役割分担です。
回答の生成と情報根拠の提示方針
AI Overviewsでは、検索結果の冒頭に生成された要約が表示されますが、その下には必ず情報源のリンクが併記されます。
これはユーザーが根拠を確認できるようにするためです。
サイト側は「引用してもらえるだけの明確な根拠や具体例」を示すことが重要で、情報の透明性や信頼性を打ち出す工夫が欠かせません。
サイト側の露出と信頼獲得の設計
SGEやAI Overviewsで取り上げられるかどうかは偶然ではありません。
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の明示、構造化データの整備、比較や手順を整理した分かりやすい記事設計などが、露出を高める要素になります。
検索体験が要約主体にシフトするほど、サイトには「一次情報や専門性のある根拠を提示する力」が求められるようになるのです。
参考サイト:AIO対策とは?SEOとの違いや具体的手法・成果指標を解説
MUMの仕組みと強みの要点
MUMは「文章を読むだけのAI」ではなく、複数の情報を組み合わせて意味を理解できるのが最大の特徴です。
多言語対応・マルチモーダル対応・少ない学習データでも一般化できる力の3つが軸になっています。
これらの仕組みにより、検索は単純な答え探しから「複雑な課題をナビゲートする体験」へ進化します。
多言語横断での知識移転
MUMはある言語で豊富に蓄積された知識を、別の言語での検索に活かすことができます。
たとえば日本語では情報が少ない新しい医療技術について調べたいとき、英語や中国語の記事にある知見を橋渡しすることで、検索者は自国語でも深い情報に触れられるようになります。
これは「情報格差を減らす仕組み」として大きな強みです。
マルチモーダル理解の活用可能性
「マルチモーダル」とは、文章・画像・動画・音声など異なる形式をまとめて理解することです。
たとえば登山靴の写真をアップロードして「この靴で冬山に行けるか」と聞けば、MUMは写真の形状や素材を読み取り、さらに記事やレビューのテキスト情報を照合して答えのヒントを出します。
文章だけでなく複数の手掛かりを組み合わせる点が、従来の検索との大きな違いです。
検索体験の変化と適用領域
MUMは「少例学習(few-shot learning)」と呼ばれる仕組みを備えており、たとえ限られた事例しか学習していなくても、新しいテーマに応用できる柔軟性があります。
これにより検索者が新しいキーワードやまだ普及していないテーマを調べても、MUMは他の分野からの知識を借りながら答えに近づくことが可能になります。
従来は情報が少ないテーマだと検索結果が薄くなりがちでしたが、この弱点を補えるのがMUMの強みです。
複雑クエリでのガイド役の強化
「予算×用途×条件」で分岐する問いに対し、比較軸の明示が価値になります。
たとえば登山装備の選定なら、季節・難易度・重量の関係を先に示します。
ショッピングとレビュー理解の高度化
レビュー要約や比較の支援では、要素分解されたデータ(スペック表、長所短所、適用シーン)が効きます。
UIが変わっても、この“骨格”は普遍です。
旅行や学習の工程設計
“いつ、どこへ、どう回るか”といった計画型のクエリで、工程・制約・持ち物を一望できる設計が選ばれやすくなります。
SEOへの影響の全体像
MUMの導入によって、SEOの焦点は「単一キーワードを狙った記事」から「テーマ全体を体系的に扱う記事群」へと広がりつつあります。
つまり、検索意図に合った1ページを書くだけでは不十分で、比較・根拠・手順を含めた一連の情報を整理して提供することが重要になります。
さらにE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の提示や、構造化データによる検索エンジンへの補助、内部リンクで記事同士を関連付ける設計など、複数の要素が組み合わさって成果につながるようになっています。
トピッククラスタと意味ネット構築
検索が複雑化する中で、単独の記事よりも「親記事と子記事のまとまり」を作ることが有効です。
たとえば「登山」というテーマなら、「登山靴」「装備一覧」「登山計画の立て方」「季節別の注意点」などを関連する記事として用意し、内部リンクで結びます。
これにより検索エンジンは「このサイトは登山に関して体系的に情報を持っている」と理解しやすくなります。
E-E-A-Tの設計と根拠提示
MUM時代は情報の信頼性がこれまで以上に重視されます。
記事を書く際は著者名や資格、情報の出典を明示し、一次情報や公式データを引用することが欠かせません。
たとえば「医療情報」や「金融情報」であれば、厚生労働省や金融庁の資料を根拠に示すことが信頼獲得につながります。
単に内容を分かりやすく書くだけでなく「誰が」「どの情報をもとに」説明しているかを読者と検索エンジンに伝えることが重要です。
構造化データと内部リンク戦略
検索エンジンは記事の意味を推測するだけでなく、構造化データを通じて明示される情報を参考にします。
FAQPageやHowToといったスキーマを設定すれば、検索結果にリッチリザルトが表示される可能性も高まります。
また、記事同士を内部リンクでつなぐ際には「関連性のある流れ」を意識し、ユーザーが自然に回遊できるように設計することが大切です。
コンテンツ設計と実装
実装は①意図分解、②比較軸の統一、③視覚情報と代替テキスト、④根拠リンクの順で進めると迷いません。
ページ単体ではなく記事群で回答を完結させます。
意図分解と記事群の役割設計
「定義→種類→選び方→比較→導入手順→運用→FAQ」という学習段階に沿って記事を並べ、相互リンクで回遊を促します。
比較軸と表現手法の統一
“価格・性能・導入難易度・適用シーン”など同じ物差しで比較表を作り、結論を先に提示します。
読者は“迷い”が減ります。
画像・動画の説明と代替テキスト
画像の意図(何を示すか)を本文と一致させ、代替テキストは機能+差分を端的に書きます。
要約キャプションを一文添えると理解が進みます。
MUM時代の主要施策と要点
| 施策 | 目的 | 実装の要点 | 効果測定の視点 |
|---|---|---|---|
| トピッククラスタ | 網羅と深度の両立 | 親子階層・内部リンク・重複排除 | クエリカバレッジ、回遊率 |
| 構造化データ | 検索理解と提示の補助 | 適切なスキーマ選定と検証 | リッチ結果発現、CTR |
| E-E-A-Tの可視化 | 信頼性の明示 | 著者・出典・更新履歴 | 指名検索、外部被リンクの質 |
| 比較・手順の明確化 | 複雑クエリの意思決定支援 | 比較軸統一、結論先出し、表・図の併用 | 滞在時間、再訪、スクロール深度 |
| 多言語・視覚情報の活用 | 知識移転と理解補助 | 画像/図表のキャプションと代替テキスト | 海外クエリ露出、翻訳流入 |
計測とモニタリング設計
計測はページ単位よりテーマ単位で。
Search Consoleのクエリをクラスタで束ね、リッチ結果と再訪・回遊を追うとMUM時代の改善ループが回しやすくなります。
クエリクラスタと意図階層の把握
検索語を“定義/比較/導入/運用/トラブル”など意図階層に分け、記事群と照合します。
欠けている段階が“次に作るべき記事”です。
リッチ結果と露出面の追跡
構造化データの検証とリッチリザルトの発現率をウォッチします。
表示が増えれば、提示レイヤー適合が進んでいるサインです。
再訪行動と内部回遊の可視化
Looker Studio等で回遊パスを可視化し、比較→導入→FAQの動線を短縮します。
数値の山谷は“意図が継げていない箇所”のヒントです。
よくある質問
実務の焦点は“いま何を変えるか”。
結論として、体系化・根拠・構造化・計測の四本柱から手を付けるのが費用対効果に優れます。
MUMは順位要因を直接置き換えるか
置き換えではありません。理解と探索支援の強化であり、ランキングの単一要因ではないと捉えるのが妥当です。
文脈理解の底上げが進んだ結果として、体系だった情報**が届きやすくなります。
画像や動画は必ず用意すべきか
可能なら用意します。
マルチモーダル理解と提示レイヤーへの適合を同時に高められるためです
代替テキストとキャプションで**内容の意味**を明確にします。
既存記事を全面改修すべきか
全面改修は不要です。まずはクエリクラスタの穴埋め、比較・手順の表現統一、構造化データの整備から段階的に進めます。
結果として“体系”が整います。
中小サイトの優先施策は何か
親テーマの要点ページ→子テーマの比較・手順→FAQの順に“核”を作ります。
E-E-A-Tの著者・出典・更新履歴を明示し、内部リンクで意味ネットを育てるのが近道です。
まとめ
検索は“単語一致”から意図と文脈の理解へ進んでいます。
MUMはその土台であり、SGE/AI Overviewsは提示の革新です。
サイト運営側はトピック体系・根拠提示・構造化・計測を柱に、読者の意思決定プロセスを助ける設計へ舵を切ると、余計な遠回りをせずに済みます。
まずは、既存記事群の**意図階層マップ**を作るところから始めてみてください。
参考文献
- Google Keyword(The Keyword)「MUM: A new AI milestone for understanding information」
- Google 検索ヘルプ「Google 検索の AI による概要で、情報をすばやく簡単に見つける」
- 生成 AI による検索体験 (SGE) のご紹介
- The Keyword「Understanding searches better than ever before(BERT)」