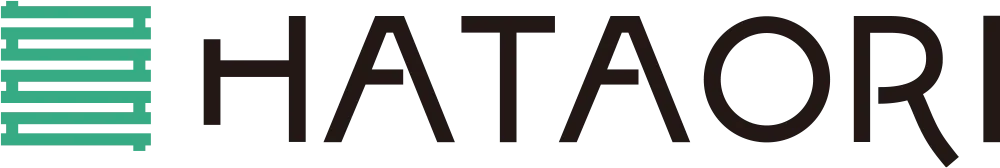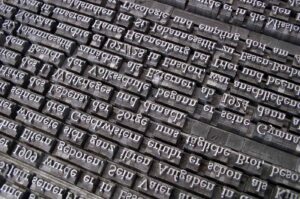RankBrain(ランクブレイン)とは?Googleのアルゴリズムや検索クエリの関係について解説
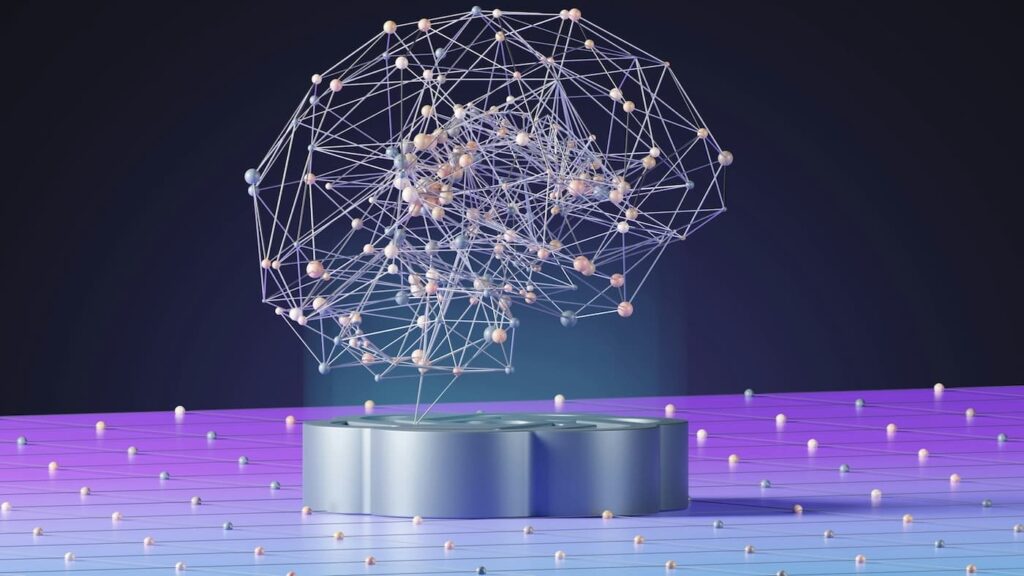
検索したときに「なぜこの結果が出てきたのだろう」と感じた経験はありませんか。裏側では、Googleが無数のアルゴリズムを使い分け、質問の意図を理解しようとしています。
その中でもRankBrainは重要な役割を担っています。少し小難しそうに見えますが、仕組みを知ればSEO対策にも直結します。
ここからは、初めての方でも安心して理解できるように順を追って整理していきます。
RankBrainとは
RankBrainは2015年頃にGoogleが導入した機械学習システムで、検索クエリとページ内容の関連性を推測する仕組みです。
今まで見たことのない検索や曖昧な表現に強みを持ちます。つまり、従来は「完全一致」でしか対応できなかった部分を補う役割を持っているのです。
ランキングシステムとの関係
検索順位はRankBrainだけで決まるわけではありません。数百種類ある評価基準のひとつであり、被リンクの評価やモバイル対応などと合わせて総合的に順位が決まります。
RankBrainはあくま「意図を理解する補助輪」のような存在です。実際にSEO対策を考えるときは、RankBrainを過大評価せず全体像を押さえることが大切になります。
参考サイト:SEO対策の外部対策とは?対策方法とサイテーションやコンテンツについて解説
BERTなど他アルゴリズムとの違い
2019年に導入されたBERTは文脈理解に特化しています。
これに対しRankBrainは、見知らぬ単語や曖昧な表現の解釈を担当します。役割が違うため、両者は競合関係ではなく協力関係です。
つまり「検索クエリの理解」はチームプレイで進められていると考えるとイメージしやすいでしょう。
検索クエリとRankBrain
RankBrainが活躍する場面は、まさに検索クエリの解釈です。
特に「見たことのない言葉」や「人によって意味が異なる表現」に対応するとき、その力を発揮します。
ここを理解すると、SEOで狙うべきキーワード設計のヒントが見えてきます。
未知語や曖昧表現の類推
たとえば「近くのおすすめカフェで落ち着ける場所」という検索。
単純なキーワード一致では拾えませんが、RankBrainは「近く=位置情報」「落ち着ける=静か、ゆったり」といった類推を行い、適切な結果を提示します。
この動きは、SEO担当者にとって「ユーザーの言い換えを先回りする」発想が必要だという意味を持ちます。
クエリの意図と推定ロジックの要点
RankBrainは検索文を分解し、関連する単語群をベクトル空間(言葉同士の距離を数値化したモデル)に配置します。
そして意味が近いものをつなげ、検索意図を推定します。
初心者には少し数学的に聞こえるかもしれませんが、要は「似たもの同士をまとめて判断する仕組み」と理解すれば十分です。
コンテンツ関連性評価への影響
RankBrainは検索クエリだけでなく、ページ内容との関連性をどう評価するかにも影響を及ぼします。
ここで大事なのは「内容を薄く増やす」のではなく、「意図に合う情報をきちんと届ける」ことです。
ページ内容とクエリの関連性
ページ内の見出しや本文が検索意図に沿っているかどうかが重要です。
たとえば「パスタの作り方」と検索した人に、材料の豆知識ばかり出しても満足しません。
RankBrainはこのギャップを見抜き、適合性を判断する役割を担っています。
ユーザー満足の代理指標と注意点
クリック率や滞在時間といった行動データも関連性の手がかりにされます。
ただし、これらは直接的なランキング要因とは限らず、あくまで参考材料です。
実際に現場で「CTRが下がったから順位が下がった」と短絡的に結びつけると誤解につながります。
E-E-A-Tとの接点
Googleは専門性・権威性・信頼性(E-A-T)に加え、経験(Experience)も重視しており、これがいわゆるEEATと言われるコンテンツの品質基準の1つです。
RankBrainが意図を理解する一方で、E-E-A-Tは「この情報は信頼できるのか」を判断する軸です。
両者を混同せずに整理すると、対策の方向性を間違えにくくなります。
RankBrainとSEO対策
ここまでの理解を踏まえると、SEOで意識すべきことが見えてきます。
それは「検索意図を正しく整理し、それに沿った情報設計を行うこと」です。
小手先のテクニックではなく、骨太な設計が求められます。
クエリと検索意図の整理
まずは検索されるクエリを集め、意図ごとにグループ分けしましょう。
「買いたい」「調べたい」「比較したい」といった違いを明確にすると、記事やページの方向性がはっきりします。
これは実務で最初にすべきステップです。
情報設計と見出しの作成方法
見出しは「検索者の質問への答え」を並べることを意識すると効果的です。
たとえば「SEO対策 方法」と検索した人には、「対策の方法」「対策に必要な考え方」「対策で必要なツール」「対策後の効果」などが答えになります。
こうして見出しを作ると、RankBrainにもしっかり意図が伝わります。
内部リンクと構造化データの活用
関連ページを内部リンクで結びつけ、さらに構造化データを設定することで、検索エンジンに「このページはこのテーマの一部です」と伝えられます。
特にFAQ構造化は効果が高く、初心者でも導入しやすい方法です。
検索意図別コンテンツ型
| 意図カテゴリ | 代表クエリ例 | コンテンツ型 | 注力ポイント |
|---|---|---|---|
| ナビゲーション | ○○ ログイン方法,登録方法 | 導線ページ | 目的地に素早く到達 |
| 情報収集 | ○○とは,○○について | ガイド記事 | 網羅性と正確性 |
| 比較・検討 | ○○ 比較, 口コミ | 比較表, 体験談 | 選択を支援 |
| 取引 | ○○ 購入, 申し込み | LP, 商品ページ | 明確な提案 |
RankBrainの歴史とアップデート
RankBrainは2015年の導入以降、検索アルゴリズム全体の一部として働いてきました。
現在ではBERTやMUMなどと並行して使われています。つまり「RankBrainだけに特化する」よりも、複数の仕組みが同時に働くと理解する方が実務的です。
導入時期と役割の変遷
導入当初は未知の検索クエリへの対応がメインでした。
その後は文脈理解の進化に合わせて役割が変化し、現在は多層的な仕組みの一部となっています。
過去を知ることで「なぜ導入されたのか」がよくわかります。
現在の位置づけと誤解の整理
いまでも「RankBrainが順位を決めている」という誤解がありますが、それは間違いです。
実際には数百の要素のひとつであり、単独で順位を動かすことはありません。
冷静に捉えると「意図理解の基盤」として見るのが正解です。
年表と主な出来事
| 年 | 出来事 | 実務での影響 | |
|---|---|---|---|
| 2015 | RankBrain導入 | 未知語に強くなる | |
| 2019 | BERT導入 | 文脈の理解が深化 | |
| 2021以降 | MUM発表 | 多言語・複数モーダル対応 |
よくある質問
Q1. RankBrainに最適化する具体策は
検索意図を整理し、それに沿った情報設計をすることが第一歩です。
用語を正しく使い、ユーザーが欲しい答えを揃えることが最も有効です。内部リンクや構造化データで補強すれば効果が高まります。
Q2. クリック率はランキング要因か
直接的な要因ではないとされています。
ただし、クリック率はユーザーの関心を測る大切なデータで、改善は間接的に評価を高める可能性があります。だから軽視はできません。
Q3. BERTとRankBrainの違いは
BERTは文章の前後関係を理解する仕組み、RankBrainは未知語や曖昧表現の意味を推測する仕組みです。
役割は違いますが、一緒に使われることで検索結果の精度を高めています。
Q4. いつから意識すべきか
すでに検索の基本として働いているため、今すぐに意識する必要があります。
特に意図を整理した情報設計は、どの時代のSEOでも役立つ普遍的なアプローチです。
まとめ
RankBrainはGoogleの検索アルゴリズムの一部であり、検索意図の理解を支える仕組みです。
SEO対策で意識すべきなのは「検索者の意図を読み取り、答えをわかりやすく届けること」です。
具体的には、クエリの整理、見出し設計、内部リンクと構造化データの活用が有効です。
すぐできる行動としては、まず自社サイトの主要クエリを意図ごとに分類し、見出しがクエリの意図に合致する内容か確認することをおすすめします。
地味な改善ですが、積み重ねることで大きな成果につながるはずです。
参考文献
- RankBrain(ランクブレイン)とは?ランクブレインの役割とSEO対策について|ディーボのSEOラボ
- RankBrain(ランクブレイン)とは?仕組みやSEO対策への影響について解説 | WEB集客ラボ byGMO(GMO TECH)
- RankBrain(ランクブレイン)とは?SEOとの関係や役割を解説 - 徹底的にSEO対策するならランクエスト
- Google 検索を支える AI 技術