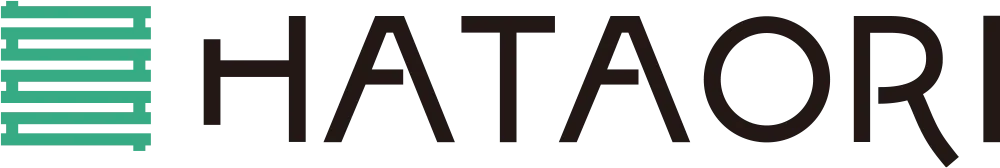記事監修とは?SEOでの重要性や依頼方法を解説
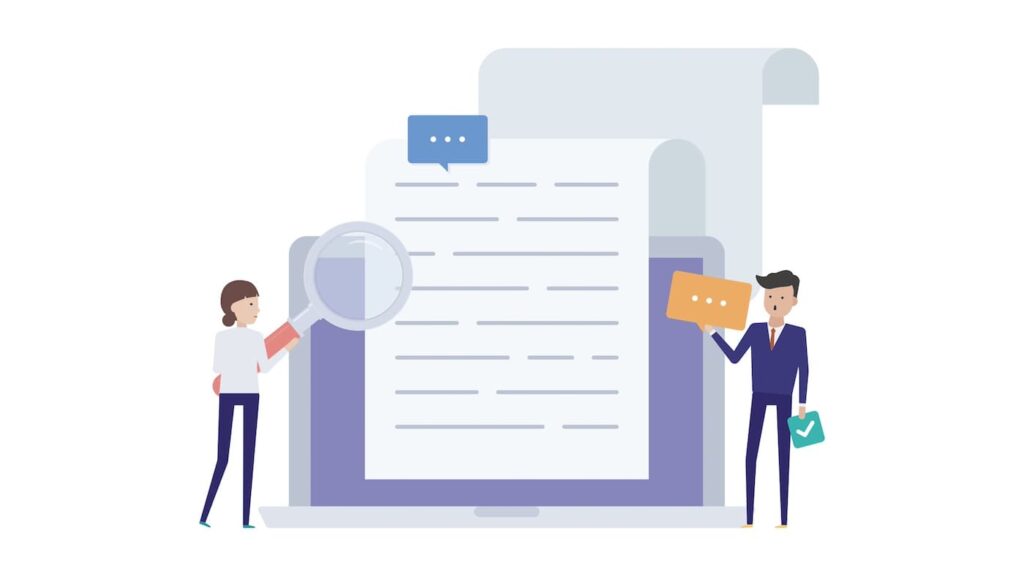
Webメディアの運営やSEO対策において、記事監修はますます重要な要素となっています。
特に医療・法律・金融といった専門性の高い領域では、検索エンジンの評価指標であるE-A-Tの観点からも、信頼できる監修者の存在が記事の価値を大きく左右します。
本記事では、記事監修の役割やSEOとの関係、監修者の探し方・依頼方法、費用感などを具体的に解説し、実際に監修を導入する際のポイントを網羅的にご紹介します。
目次
記事監修とは
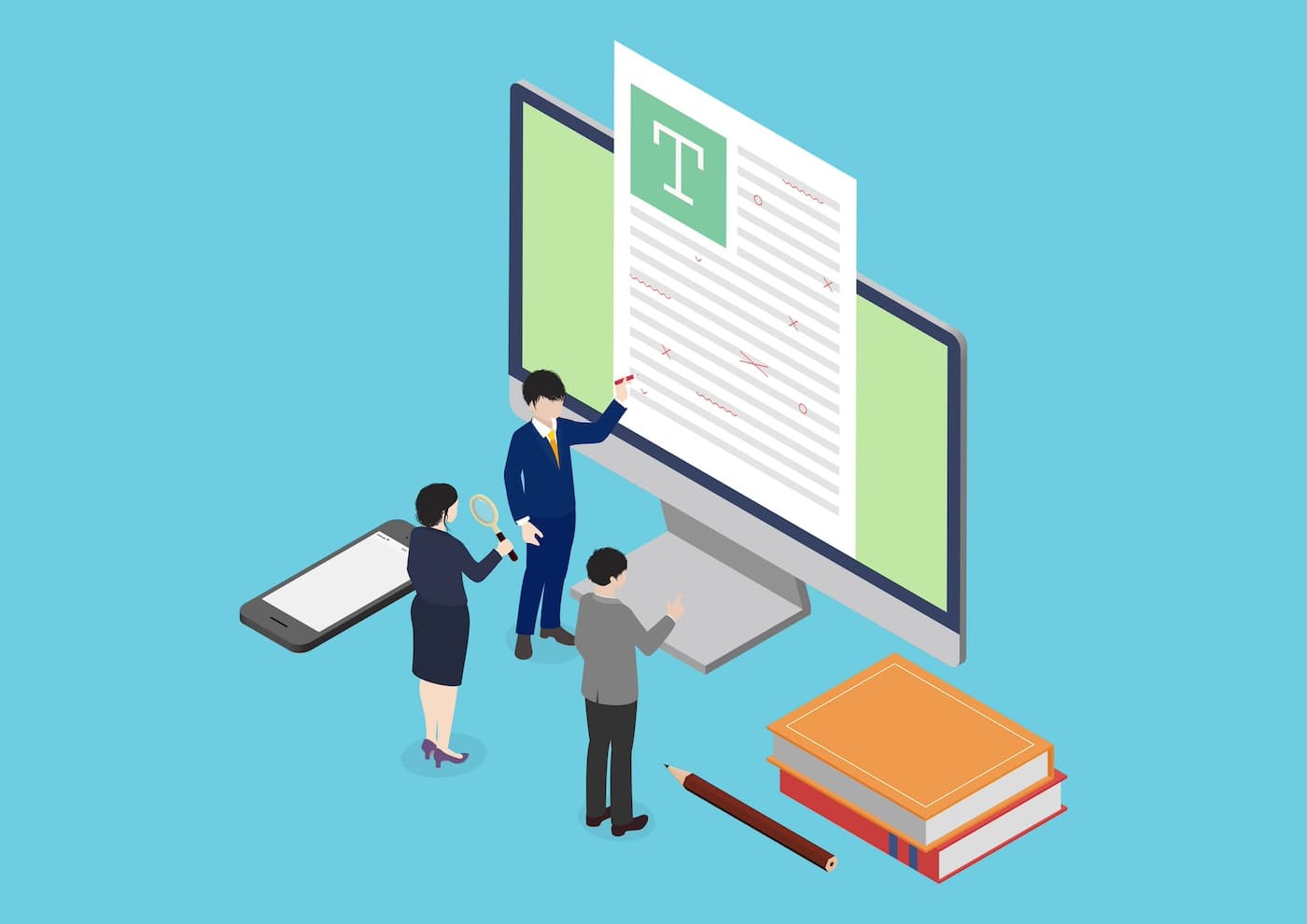
記事監修とは、専門知識を持つ第三者が記事内容をチェックし、正確性や信頼性を担保するプロセスです。
SEO対策や情報の信頼性向上に欠かせない手段として、注目が高まっています。このセクションでは、記事監修の基本的な役割や意味を解説します。
記事監修の役割
記事監修の主な役割は、記事内の情報が事実に基づいているか、専門的な見地から適切かを確認することです。
たとえば、医療系の記事で「●●というサプリには美肌効果が期待できる」といった表現があれば、それが科学的根拠に基づいているかを医師が監修します。
読者は検索結果から得た情報を信じやすいため、誤情報や偏った見解がそのまま広まるリスクがあります。
そこで、信頼できる専門家が記事に目を通し、情報の正確性を担保する必要があるのです。記事監修は「記事に対する責任の明確化」という意味でも重要です。
監修者名を明記することで、執筆者だけでなく第三者の目が入っていることを示し、読者や検索エンジンの信頼を獲得しやすくなります。
次項では、なぜ記事監修がSEOにおいても重要なのか、その必要性について詳しく解説します。
記事監修がSEO対策における必要性

記事監修は、単に正確な情報を担保するだけでなく、SEOの観点からも非常に大きな意味を持ちます。このセクションでは、読者が「なぜ監修がSEOに有効なのか」「どうすれば効果的に活用できるのか」といった疑問を解決できるように、詳細に解説していきます。
SEO対策のおける記事監修の役割
記事監修の目的は、専門家の視点から情報の正確性と中立性を確保することにあります。
たとえば医師が監修することで、誤解を招く健康情報を排除でき、読者にとっても安心感があります。
これにより、読者の滞在時間や回遊率が向上し、SEO上の評価にも良い影響を与えるのです。
また、監修者が名義を出すことで記事の信頼性が可視化されます。
これは、Googleが重視するE-A-Tの「信頼性」に直結し、特に医療・金融・法律などのYMYL(Your Money or Your Life)ジャンルでは欠かせない対策となっています。
SEO対策の効果はどの程度か
結論から言うと、記事監修はSEOにとって非常に有効です。
Googleは検索品質評価ガイドラインにおいて、E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を重視していると明言しています。
特に医療や法律、金融などの分野では、専門家による監修があるかどうかがSEO評価のポイントになるケースが増えています。
具体的には、以下のような点で効果が期待できます。
- 信頼性のある情報源としてGoogleに評価される
- 読者の離脱率が下がり、エンゲージメントが向上する
- 被リンクされやすくなる(信頼ある情報は他サイトでも紹介されやすい)
つまり、記事監修はSEO順位の直接的・間接的な要因を底上げする施策のひとつとして機能します。
監修者の探し方や依頼方法、相場
「監修者ってどうやって探すの?」「費用はどれくらい?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。監修者の探し方には複数の方法があります。
クラウドソーシング(例:ランサーズ、クラウドワークス)で専門家を検索
専門家紹介サービス(例:監修ドクター)を利用する
大学の研究者や士業事務所へ直接依頼する
相場は以下のように内容やジャンルによって大きく異なります
項目
相場の目安
記事単位
5,000円〜30,000円
文字数単位
1文字あたり2円〜10円
専門性の高いジャンル(医師・弁護士など)
高額傾向
依頼時には、記事の内容や文字数、希望する監修範囲を明確に伝えることが成功のポイントです。また、契約時に監修者名の表記許可や修正対応の範囲も確認しておきましょう。
編集者とプロデューサーとの違い
「編集者」や「プロデューサー」と混同しがちな「監修者」ですが、それぞれ役割が大きく異なります。
監修者:専門知識をもとに内容の正確性をチェックする人。あくまで内容の監修が目的で、文章表現や構成には基本的に関与しません。
編集者:ライターが執筆した原稿の内容や構成をチェックし、読みやすく仕上げる役割を担います。SEO的な見出し構成や文法チェックも編集者の仕事です。
プロデューサー:記事全体の企画立案やスケジュール管理、外注スタッフのディレクションなど、制作工程全体をコントロールします。
それぞれの役割を理解し、目的に応じて適切な人材をアサインすることが、質の高いコンテンツ制作のカギとなります。
記事監修の具体的な業務内容

記事監修では、単なる誤字脱字のチェックではなく、専門的な視点での内容精査や読者への影響を考慮した表現の最適化が求められます。
このセクションでは、監修者が実際に行う業務を3つの観点から詳しく解説します。
事実確認:内容に誤りがないかをチェック
記事監修において最も基本的かつ重要な業務が「事実確認」です。
特に医療・法律・金融などの専門領域では、間違った情報を公開することが読者の誤解を招き、場合によってはトラブルや損害につながる恐れもあります。
たとえば医療系の記事で「風邪に抗生物質が効く」と誤って書かれていた場合、それを鵜呑みにした読者が不要な薬を求めてしまう可能性もあります。
このような誤情報を未然に防ぐのが監修者の役割です。
また、情報の出典が不明確な部分に対して「信頼できる情報源があるか」「データは古くないか」といった観点から確認・修正の提案を行います。
こうした対応によって、記事全体の信頼性が大幅に向上します。
表現の調整:専門用語や法的表現などを正しくわかりやすくする
専門的な内容であればあるほど、読者に伝わりやすい表現への変換が求められます。
監修者は、専門家として正確な知識を持ちながらも、それを「読者目線」で翻訳するような役割も担います。
たとえば、法律記事で「債務不履行」「履行遅滞」といった専門用語をそのまま使うと、一般の読者には理解しづらくなります。
監修者はこれらの用語に対して「借金の返済が遅れること」「約束を守れなかった場合」といった形でわかりやすい解説を加える提案を行います。
また、難解な専門表現や冗長な文章を整理し、よりスムーズに読み進められるように文章の構造を調整することもあります。
倫理的配慮:誤解を生む表現や偏った情報の排除
現代では、多様性やジェンダー、宗教、障害、病気など、読者の価値観に配慮した文章表現がますます重要になっています。
監修者は記事の表現が一方的・差別的でないか、特定の立場を不当に支持していないかといった点をチェックします。
たとえば、健康に関する記事で「〇〇を食べれば絶対に痩せる」といった過剰な断言は誤解を招く可能性があります。
これを「〇〇には脂肪燃焼を助ける成分が含まれるとされますが、個人差があります」といった中立的かつ根拠のある表現に修正する必要があります。
また、メンタルヘルスや病気に関する内容では、患者本人や家族の気持ちに配慮した表現が必要です。誤解や偏見を助長しないようにするためにも、監修者の視点が不可欠です。
監修が必要とされる記事ジャンル

監修はすべての記事に必要というわけではありませんが、特定のジャンルでは読者の信頼性を担保するために非常に重要です。
とくに医療・法律・金融などの「YMYL(Your Money or Your Life)」に該当するジャンルでは、専門家の監修が必須とされています。
このセクションでは、監修が必要とされる代表的なジャンルを具体的にご紹介します。
医療・健康系(例:病気、治療、薬の解説)
医療や健康に関する記事は、読者の命や生活に直結する重要なテーマです。
そのため、誤った情報や過度な表現があると、重大なリスクを引き起こす恐れがあります。
たとえば、「〇〇を食べるだけでがん予防になる」といった断定的な表現や、医薬品の効能についての不正確な説明は、薬機法(旧薬事法)に違反する恐れもあります。
監修者は医師、薬剤師、管理栄養士などの資格を持った専門家が望ましく、医学的根拠に基づいた記述へと内容を調整してくれます。
法律系(例:労働法、相続、契約書)
法律に関する記事も、読者の行動や判断に大きな影響を与えるため、正確性が求められます。
特に労働問題や相続、契約トラブルなどのジャンルでは、誤った解釈や古い法律に基づいた情報を提供することで、読者が損害を被るリスクもあります。
このような分野では、弁護士や司法書士、行政書士などの資格保有者による監修が望まれます。
記事に監修者の肩書きや所属が明記されていることで、読者からの信頼を得やすくなります。
金融系(例:投資、保険、税金)
金融に関する記事は「お金の意思決定」に直接関係するため、Googleのガイドラインでも特に注意が必要とされる分野です。
投資商品の比較や保険選び、税金の解説といった内容は、信頼できる情報源であることが検索評価にも影響を与えます。
たとえば、ファイナンシャルプランナー(FP)や税理士などが監修者として参加することで、専門性と信頼性が高まります。
読者は安心して記事を読み、判断材料にすることができるようになります。
教育・学術系(例:大学受験、専門分野解説)
教育や学術分野でも、内容の正確性は重要です。
特に受験情報や進路に関わる記事では、過去の制度や誤った解釈が掲載されていると、読者にとって有害となることもあります。
たとえば、大学教授や教育カウンセラー、現役の教師などが監修を行うことで、より最新かつ正確な情報に基づいた記事を提供できます。
学術的な解説についても、誤解を招かないよう専門的な用語の補足や表現調整が必要です。
記事監修とE-A-Tの関係

E-A-Tとは、Googleがコンテンツ評価において重視する「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取った言葉です。
特にYMYL(Your Money or Your Life)ジャンルにおいては、E-A-Tの高さが検索順位を左右すると言われており、記事監修はそのE-A-Tを高めるための重要な施策のひとつです。
このセクションでは、E-A-Tの定義を改めて整理し、なぜ監修がその向上に寄与するのかを具体的に解説します。
参考:EEATとは?SEO対策で重視されるGoogle品質評価基準と対策方法について解説
Googleが重視する「E-A-T」とは
Googleは公式に「高品質な検索結果を提供する」ことを目指しており、その基準のひとつがE-A-Tです。
とくにYMYLジャンルでは、読者に誤った情報を与えないよう、信頼できるコンテンツかどうかを慎重に判断しています。
たとえば、医療情報を専門知識のないライターが執筆した場合、その正確性に疑問が生じます。
Googleはこうしたケースでは評価を下げる傾向にあり、逆に監修者として医師の名前が明記されている場合には、信頼性が高いと判断し、検索順位にも好影響をもたらします。
E-A-Tの定義と意味
Expertise(専門性):書き手または監修者の専門知識
「専門性」は、そのコンテンツが特定の分野においてどれだけ正確で深い知識に基づいているかを評価する要素です。
記事の筆者だけでなく、監修者の肩書きや資格もGoogleは評価対象としています。
たとえば、医療に関する記事で「医師監修」の明記があれば、それだけで専門性が高いと認識されます。
専門性の高い人物がチェックしていることで、コンテンツ全体の精度が保証されていると判断されるためです。
Authoritativeness(権威性):業界や検索者からの評価
「権威性」は、発信者が業界内や読者からどれだけ信頼されているかを指します。
実績、メディア露出、所属団体、SNSでの評価なども間接的に影響します。
監修者が有名な医師や、学会所属の研究者、実績ある弁護士である場合、その名前が掲載されているだけでコンテンツの評価が上がります。
読者も「この人が言っているなら間違いない」と判断しやすくなります。
Trustworthiness(信頼性):内容の正確性と情報源の明確さ
「信頼性」は、コンテンツが正確であり、出典や参考情報が明記されているかどうかで判断されます。
監修者がいることで、記事が一方的な主張に偏ることなく、公平で正確な情報に基づいていると証明できます。
また、監修者の肩書きや所属機関、プロフィールページへのリンクがあることで、ユーザーはその人物が本当に信頼できるかを確認でき、結果としてページ全体の信頼度も向上します。
参考:EEATとは?SEO対策で重視されるGoogle品質評価基準と対策方法について解説
記事監修がE-A-Tに与える影響

記事監修は、Googleが重視するE-A-T(専門性・権威性・信頼性)を高めるうえで非常に有効です。
このセクションでは、監修者を明記することで得られる具体的なSEO効果や、どのような工夫でE-A-Tを強化できるかを詳しく解説します。
監修者の名前とプロフィールを明記することで、専門性と権威性が強化される
監修者の氏名、肩書き、所属機関などを記事中に明記することで、Googleに対して「この記事は専門家のチェックを受けている」と明確にアピールできます。
これは特に、専門性(Expertise)と権威性(Authoritativeness)の強化につながります。
たとえば、「〇〇クリニック 院長 医学博士 田中一郎先生監修」と記載し、プロフィールページやクリニックの公式サイトへのリンクを設置することで、Googleクローラーがその人物の信頼性や実在性を確認しやすくなります。
また、読者にとっても「信頼できる人が見てくれている」という安心感につながり、コンテンツの価値が高まります。
情報源としての信頼性が高まり、検索エンジンから高評価を受けやすくなる
監修者がいることで、記事の内容が一方的な主張や誤情報ではなく、信頼できる情報源に基づいていると示すことができます。
これにより、E-A-Tのうちの「信頼性(Trustworthiness)」が大きく向上します。
特に、出典や根拠となる資料・法令・統計などをしっかりと記載したうえで、専門家がそれを確認・承認しているという事実は、Googleのアルゴリズムに対しても「安心して上位表示できるページ」として働きます。
加えて、医療や法律などリスクのある情報分野においては、監修の有無が検索順位を左右するケースも少なくありません。
YMYL領域では監修が事実上の必須に
YMYL(Your Money or Your Life)領域とは、「人々のお金や生活・健康・安全などに大きな影響を与える可能性のある情報領域」のことを指します。
このジャンルでは、Googleの評価基準が非常に厳しく、監修が入っていない記事は上位表示されにくくなっています。
たとえば、「ダイエット中に摂取すべき栄養素」といった健康に関わる情報や、「確定申告の方法」といった税金に関する内容は、専門家による監修がなければ不正確な情報と見なされるリスクがあります。
こうした背景から、監修者を起用することは、YMYLジャンルでは「任意」ではなく、ほぼ「必須」と言える施策になりつつあります。
監修者・編集者・プロデューサーの違い

記事制作に関わる「監修者」「編集者」「プロデューサー」は、いずれも重要な役割を担っていますが、それぞれの職務内容や責任範囲は異なります。
ここでは、混同されがちな3つのポジションの違いを明確にし、どのように役割分担すべきかを解説します。
監修者:専門的知識による内容の正確性チェックが主業務
監修者は、専門知識に基づいて記事の内容をチェック・修正し、情報の正確性と信頼性を担保する役割を担います。
医師や弁護士、税理士、大学教授など、専門資格を持つ人物がこの役割を担うケースが多く、YMYLジャンルでは欠かせない存在です。
たとえば医療系の記事では、「この薬の効果」や「病気の症状」などについての記述が正しいかどうかを確認し、場合によっては表現の修正や補足を行います。
監修者は記事の信頼性に直接影響するため、SEO上でも非常に重要な役割です。
編集者:記事構成、タイトル設定、読みやすさや文法のチェックが主業務
編集者の主な役割は、記事の構成・文章の流れ・表現の分かりやすさを調整し、読みやすい記事を作ることです。
文章全体のクオリティ管理やSEOを意識したキーワード調整、タイトル・見出しの最適化などを行うこともあります。
たとえば、同じ内容であっても「読者が理解しやすい順序に並び替える」「難解な言葉をやさしく言い換える」といった工夫は編集者が行います。
また、Google検索に強い記事を作るための意図的な構成調整も編集者の領域です。
プロデューサー:企画立案、スケジュール管理、チームマネジメントなど
プロデューサーは、記事やメディア全体の企画・方針決定から、制作スケジュールの管理、ライターや編集者、監修者のアサインまで、プロジェクト全体を俯瞰して進行する立場にあります。いわば“指揮者”のような存在です。
たとえば「春に向けた健康特集記事を月末までに20本仕上げる」といったゴールを設定し、誰が何をいつまでにやるべきかを決めて調整していくのがプロデューサーの仕事です。
SEOやマーケティングの知見も必要になるため、戦略的な役割を担うことが多いです。
役割の違いを比較表で整理
| 役割 | 主な業務内容 | 関与範囲 | 関与時期 |
|---|---|---|---|
| 監修者 | 内容の正確性確認、専門的修正 | 記事の専門的内容 | 記事完成前後 |
| 編集者 | 文章構成、文法チェック、SEO調整 | 記事全体の読みやすさ・SEO | 執筆前~公開前 |
| プロデューサー | 企画立案、スケジュール管理、メンバーアサイン | 制作全体の進行管理 | 企画段階から |
記事監修の費用相場と依頼方法

記事監修を依頼する際に最も気になるのが「費用相場」と「どうやって依頼するか」という点ではないでしょうか。
このセクションでは、相場感の理解と依頼方法の流れを詳しく解説します。
記事監修の相場感
記事監修の費用は、ジャンルや専門性、記事の分量、監修の範囲などによって大きく異なります。
以下に、一般的な料金体系を紹介します。
記事単位:1記事 5,000円〜30,000円(専門性により変動)
もっとも一般的なのが「記事単位」の料金設定です。たとえば、以下のような価格帯が多く見られます。
- 一般的な内容(例:美容や生活系):5,000円〜10,000円
- 専門性の高い内容(例:医療・法律・税金など):15,000円〜30,000円
この料金には、記事全体の確認や簡単な修正、コメントの記入が含まれるのが一般的です。
記事が複雑だったり、画像や図表の監修が必要な場合は、さらに高額になることがあります。
文字数単位:1文字 2〜10円程度
一部では「文字単価」での監修も行われています。
たとえば、2,000文字の記事なら4,000円(2円×2,000文字)〜20,000円(10円×2,000文字)程度です。
こちらは記事の長さに応じた明瞭な料金計算がしやすく、両者にとって管理が楽な形式です。
監修者の相場に影響する要素
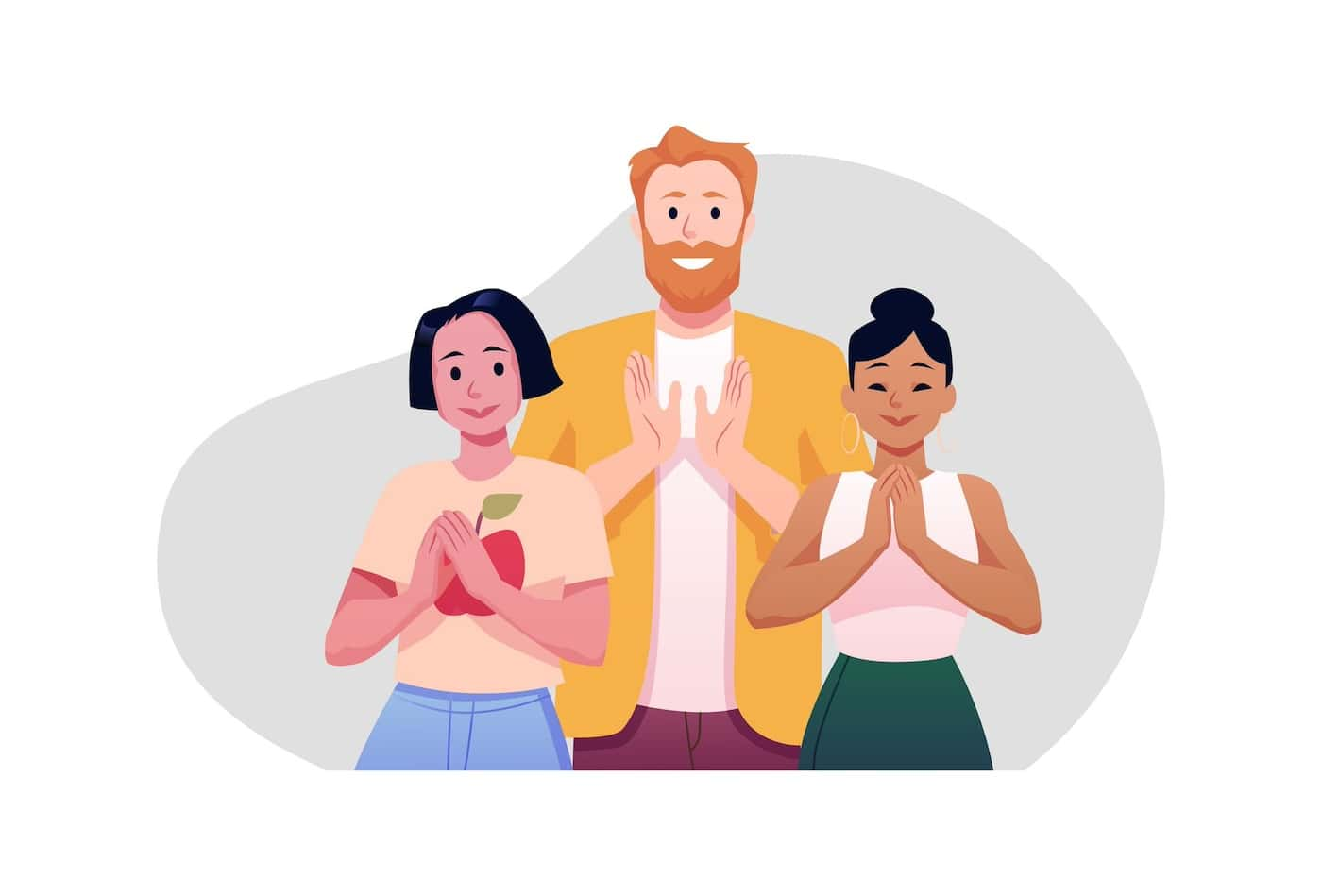
監修費用は一律ではなく、複数の要素によって決まります。
依頼前に、以下のポイントを確認しておくことが重要です。
専門性の高さ(医師・弁護士などは高額)
専門的な資格を持つ監修者は、責任が重いため、報酬も高くなります。
特に医師や弁護士、税理士といった国家資格を有する職種は、1記事あたり3万円以上になることも珍しくありません。
これは、その人物の信用が直接記事の信頼性を支えるためです。
記事の長さと難易度
当然ながら、記事が長ければ長いほどチェックにかかる時間が増え、費用も高くなります。
また、専門的で細かい内容であるほど、確認に要する知識と労力が求められ、価格も上昇します。
監修の範囲(事実確認のみ/修正・コメントまで含む など)
監修業務の範囲が広くなるほど、費用も高くなります。たとえば、
- 事実確認のみ:比較的安価(例:5,000円〜)
- 表現修正・補足コメントも含む:中価格帯(例:10,000〜20,000円)
- 原稿の書き直し・文体調整まで行う:高価格帯(例:30,000円〜)
というように、作業の深さで価格が変わります。
監修者の探し方と依頼の流れ

監修を依頼するには、まず適切な専門家を見つける必要があります。そのためには複数のルートを活用することが効果的です。
ここでは、監修者の探し方と、依頼から契約、納品までの一連の流れを詳しく解説します。
監修者の探し方
監修者を探すには、信頼できる情報源やプラットフォームを活用するのがポイントです。
以下に代表的な方法を紹介します。
クラウドソーシング(例:ランサーズ、クラウドワークス)
クラウドソーシングは、専門家と直接やり取りできる手軽な手段です。
特にランサーズやクラウドワークスでは、医師や士業などの資格保有者が登録していることも多く、プロフィールや実績を確認した上で依頼できます。
ただし、登録者数が多いため、適切な人物を見極めるには時間がかかることがあります。
事前に実績やレビュー、ポートフォリオなどをしっかりチェックするようにしましょう。
専門家紹介サービス(例:監修ドクター)
「監修ドクター」などの専門家紹介サービスを利用すれば、業種に特化したプロフェッショナルを紹介してもらえます。
信頼性が高く、事前にスクリーニングされていることが多いため、品質面でも安心です。
費用はやや高めになる傾向がありますが、専門性や実績が確保されているため、医療や法律など高リスクジャンルでは有効な選択肢です。
大学や士業事務所への直接依頼
大学の研究者や弁護士・税理士事務所に直接依頼する方法もあります。
特に信頼性を重視する場合、肩書きや所属が明確な方に依頼するのは効果的です。
Webサイトや研究業績などからアプローチすることが可能です。
依頼時には丁寧な説明と依頼書を添えることで、真摯な姿勢を伝えることが大切です。
SNSやnoteで実績ある専門家にDM
最近では、SNSやnoteを通じて活動している専門家も増えています。
たとえば、医師が健康情報を発信していたり、税理士がマネー記事を書いているケースなどがあります。
これらの人たちに直接DMで依頼するのも一つの手段です。ただし、やりとりには誠実さと信頼性が求められます。
依頼文では、記事の概要や目的、報酬、納期などを明確に伝えることが重要です。
監修者への依頼の流れ
依頼から監修完了までの一般的なステップを紹介します。スムーズに進めるためには、事前準備と明確な連絡が欠かせません。
- 監修者候補のリストアップ
まずは依頼するジャンルに適した監修者を複数ピックアップしましょう。専門性や対応実績を比較検討します。 - 監修対象記事・業務内容を明示した上で見積もり依頼
記事の内容、監修の範囲、納期、希望する対応レベル(チェックのみか、修正・コメント含むか)などを記載して問い合わせましょう。 - 契約書締結(業務委託契約)
契約の際は、報酬、納期、修正回数、著作権や監修名表記の扱いなどを明確に記載します。トラブル防止のため、書面で交わすのが理想です。 - 記事を共有・フィードバック受領
記事データ(WordやGoogleドキュメントなど)を共有し、フィードバックをもらいます。質問があれば、追って連絡しましょう。 - 修正・公開
監修結果を反映して修正し、内容が整ったら公開します。必要に応じて、監修者の氏名や肩書きをクレジットに記載します。
監修者との契約時の注意点

監修者に依頼する際には、業務の進行中や後でトラブルにならないよう、契約内容を明確にしておくことがとても重要です。
ここでは、契約時に注意すべき具体的なポイントを紹介します。
報酬と納期の明確化
まず最も大切なのは、報酬と納期について明確に取り決めることです。
曖昧なまま契約してしまうと、後から「この作業は報酬に含まれていない」「納期が間に合わない」などのトラブルにつながる可能性があります。
たとえば、報酬は「記事1本あたりの金額」とするか「文字数単位の報酬」とするかを決め、合計金額を提示します。
また、納期も「初回提出日」「フィードバック締切」「最終納品日」と複数段階に分けて指定しておくことで、スムーズな進行が可能になります。
修正回数と対応範囲の明記
記事監修では、初回の確認後に追加の修正が発生することがあります。
そのため、修正対応が何回まで含まれるのか、どの範囲まで対応してもらえるのかを事前に決めておくことが大切です。
たとえば「2回までの修正対応込み」「原則、事実確認に限定し、表現変更は対象外」など、対応範囲と制限を明確に契約書に記載します。
これにより、業務量の増加による報酬トラブルを防ぐことができます。
監修者名・肩書きの表記許可の有無
監修者を起用する目的の一つが、「専門性や信頼性のアピール」です。
そのため、記事内に監修者の氏名や肩書きを記載できるかどうかも、必ず確認しましょう。
場合によっては、実名ではなく「某大学教授」「現役弁護士」など匿名での対応を希望する専門家もいます。
事前に表記方法の可否を確認し、承諾を得ておくことで、公開後のトラブルを防げます。
比較表:契約時の注意点まとめ
| 項目 | 内容の例 | 注意点 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 報酬 | 記事1本10,000円/1文字5円など | 業務内容とのバランスを確認し、合意の上で決定 |
| 納期 | 初稿提出日、最終納品日などを明記 | 途中の確認スケジュールも含めて設定 |
| 修正対応 | 2回まで無料、それ以降は追加費用など | 修正範囲も明確にし、事前合意を取る |
| 名前・肩書きの表記 | 実名掲載可/不可、肩書き記載方法など | 公開後のトラブル防止のため、明示的な同意を取ること |
記事監修を導入することで、SEO対策やブランドの信頼性向上に繋がるだけでなく、コンテンツの質そのものが大きく向上します。
ここでは、記事監修を導入することによって得られる主なメリットについて解説します。
SEO・ブランディング上のメリット
記事に専門家の監修を加えることで、SEOやブランドの認知度に対して直接的な効果が得られます。
監修者が認知度の高い専門家であれば、コンテンツ自体の信頼性が格段にアップし、Googleなどの検索エンジンでも評価が高まりやすくなります。
SEOの観点からのメリット
Googleは、E-A-T(専門性、権威性、信頼性)の観点で評価を行っています。
特に「YMYL(Your Money Your Life)」に関連するコンテンツ(医療、法律、金融など)では、E-A-Tが重要な要素となります。
専門家による監修を加えることで、Googleに対してそのコンテンツが信頼できる情報であることを証明でき、検索順位向上が期待できます。
ブランディングの向上
また、監修者を起用することで、自社メディアやブランドの専門性と信頼性を強化できます。
特に医療や法律関連のメディアでは、著名な専門家を起用することで、業界内での権威が高まり、信頼性のあるメディアとして認知されやすくなります。
記事の信頼性・専門性が向上し、読者の安心感を得られる
監修を導入することで、読者に対して「この情報は信頼できる」と感じさせる効果があります。
特に専門的な内容や難解な情報を提供する記事では、監修者の名前や経歴があることで、読者に安心感を与え、さらに記事の内容を信じてもらいやすくなります。
たとえば、健康や金融に関する記事の場合、誤った情報や不完全な情報があると、読者に大きな影響を与える可能性があります。
そのため、専門家によるチェックや監修があることで、情報の正確さと信頼性が保証され、読者が安心してコンテンツを消費できるようになります。
Google評価が高まり、検索順位が上がる可能性がある
記事監修を導入することで、SEO上での大きなメリットがあります。
Googleは、専門家や信頼できるソースによるコンテンツを優先的に評価します。
これにより、監修者が信頼のおける専門家であることが確認されると、コンテンツの評価が高まり、検索エンジンのランキングで上位に表示される可能性が高くなります。
特に、SEO対策の一環としてE-A-Tを強化することは、検索順位を向上させるために非常に重要です。
専門家が監修することにより、コンテンツの信頼性と権威性が高まり、その結果、SEO効果が期待できるのです。
ブランドとしての権威性を築ける(特に医療・法律系メディア)
医療や法律、金融など、特に専門性が求められる分野では、信頼性が最も重要な要素です。
このような分野では、監修者が著名な専門家であれば、そのブランドとしての権威性を確立することができます。
ブランドが信頼され、知名度が上がることで、顧客や読者に対する影響力が増し、競合他社と差別化できるのです。
たとえば、医療メディアにおいては、監修者として有名な医師を起用することが、そのメディアの信頼性と価値を大きく向上させます。
同様に、法律や金融系のメディアでも、業界内で権威のある専門家を監修者として迎えることで、メディア全体の信頼性と影響力を強化できます。
監修を導入すべきタイミング
記事監修を導入するタイミングは、コンテンツの内容や目的によって異なりますが、いくつかの具体的なタイミングが考えられます。
以下では、監修が特に重要となる場面を紹介します。
医療・法律・金融などYMYLジャンルの記事を制作するとき
医療、法律、金融などのYMYL(Your Money Your Life)ジャンルの記事は、検索エンジンにおいて非常に厳しい評価基準が設けられています。
このようなジャンルでは、情報の正確性や信頼性が最も重要な要素です。したがって、専門家による監修は必須と言えるでしょう。
監修者を起用することで、コンテンツが信頼できるものであると認識され、検索順位に好影響を与えることができます。
信頼性の高い情報発信が求められるジャンルで上位表示を狙うとき
医療や法律に限らず、消費者にとって信頼性の高い情報が求められるジャンルでは、監修者を起用することが非常に効果的です。
特に、競争が激しい業界では、信頼性を確保することで他のサイトとの差別化が可能になります。
例えば、商品レビューサイトや健康情報を提供するサイトでは、監修者の名前を明記することで、読者に安心感を与え、クリック率やコンバージョン率の向上が期待できます。
既存記事が検索順位で苦戦しており、E-A-Tの強化を図りたいとき
既存の記事がSEOで苦戦している場合、E-A-Tを強化することが効果的です。
この場合、記事の監修を導入することで、コンテンツの専門性、権威性、信頼性を高めることができます。
監修者の追加により、Googleの評価が改善され、検索順位が向上することが期待できます。
まとめ:記事監修はSEO対策の有効な武器
記事監修を導入することは、SEO対策の一環として非常に効果的です。
専門家による監修を受けることで、コンテンツの信頼性や専門性を高め、GoogleのE-A-T評価を強化することができます。
特にYMYLジャンルでは監修が欠かせない要素となります。また、ブランド力の向上にもつながり、SEOや読者の信頼を得るためには非常に有効な手段と言えるでしょう。
監修者を選ぶ際は、その専門性や実績をしっかり確認し、契約内容を明確にしてトラブルを避けるようにしましょう。
適切なタイミングで監修を導入し、SEOやコンテンツの質を向上させましょう。