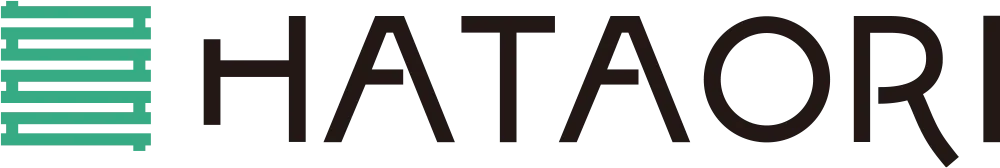ペルソナ設計とは?ターゲットを絞る方法と分析方法を解説

マーケティングや商品開発において、「誰に届けるのか」を明確にすることは成功のカギを握ります。
その鍵を握る手法のひとつが「ペルソナ設計」です。しかし、「ペルソナってよく聞くけれど、どうやって設計すればいいの?」「ターゲットと何が違うの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ペルソナ設計の基本的な意味から、実務に役立つ具体的なステップ、分析に使える方法やツール、そしてBtoB・BtoCでの違いまでを網羅的に解説します。
「伝わるマーケティング」を実現するために、まずはペルソナ設計の基礎から始めていきましょう。
目次
ペルソナ設計とは?基本の意味と目的
ペルソナ設計とは、理想的な顧客像を具体的に描くことで、マーケティングやプロダクト開発に役立てる手法の一つです。
本セクションでは、ペルソナ設計の基本的な意味や目的、そして混同されがちな「ターゲット」との違いについて解説します。
ターゲットとの違い
ターゲットとは「20代女性・都内在住・独身」といった属性情報を元にした大まかな顧客層を指します。
一方、ペルソナは、特定の名前や職業、ライフスタイル、価値観、趣味嗜好までを含めた“1人の架空の人物”です。
つまり、ターゲットが「誰に向けて発信するか」という集合的な視点であるのに対し、ペルソナは「その中でも最も象徴的なユーザー像」を指す具体的な個人像です。
たとえば、ターゲットが「30代前半の会社員女性」だとすれば、ペルソナは「田中恵美さん(32歳・東京在住・広告代理店勤務・趣味はヨガ)」のような形で詳細に設定されます。
このように具体化することで、マーケティング施策やコンテンツ設計の際に、より「人に響く」コミュニケーションが可能になります。
ペルソナ設計の目的と効果
ペルソナ設計には複数の目的と効果があります。
本章では「ユーザー理解の精度向上」「一貫性のあるマーケティング施策の実現」「社内やクライアントとの認識統一」という3つの観点からその重要性を解説します。
ユーザー理解の精度を高める
漠然としたターゲット像では、ユーザーがどんな背景を持ち、どのような課題や動機を持っているのかまで把握するのは困難です。
そこでペルソナ設計を行うことで、「この人なら何に悩み、どんな行動をとるか」といった具体的な仮説を立てることが可能になります。
たとえば、BtoCのファッション通販サイトであれば、「休日にカフェ巡りが好きな20代女性」といったペルソナを想定することで、SNS施策やLPのビジュアル選定、コピーライティングのトーンが一貫し、ユーザーの共感を得やすくなります。
一貫性のあるマーケティング施策
ペルソナ設計を行うことで、プロモーションやコンテンツ制作、商品開発など、部門ごとの施策に一貫性を持たせることができます。
全員が同じユーザー像を意識していれば、メッセージのズレが少なくなり、ブランドとしての信頼感も高まります。
たとえば、「インスタで映える美容アイテムを探している大学生女性」というペルソナをもとに、SNS投稿からECサイトまで同じトーン&マナーで展開することで、ユーザー体験が滑らかになります。
社内・クライアントとの認識統一
プロジェクト関係者が多い場合や、外部のクライアントと連携して進行する場合に、ペルソナは共通言語として非常に有効です。
「誰に向けて何を届けるか」という視点を明確に共有できるため、議論のブレが減り、施策の方向性も揃いやすくなります。
たとえば、新しいブランドサイトを制作する際に、クライアントと「誰向けのサイトか」という認識が食い違うと、デザインやコンテンツがまとまらなくなることがあります。
あらかじめペルソナを共有しておくことで、意見のズレを防ぐことができます。
ペルソナ設計の手順
ペルソナ設計には一定のプロセスがあります。ここでは5つの基本ステップと、情報収集に役立つ具体的な方法やツールについて解説します。初心者でも順を追って進めることで、質の高いペルソナ設計が可能になります。
ペルソナ設計の基本ステップ
1. 目的を明確にする
最初のステップは、ペルソナ設計の目的をはっきりさせることです。
自社の商品・サービスにおいて「誰の課題を解決したいのか」「どのチャネルに活用するのか」といった目的が曖昧だと、的外れなペルソナになりかねません。
たとえば、ECサイトの購入率を上げたい場合と、オウンドメディアの読者数を増やしたい場合では、設計すべきペルソナの焦点が変わってきます。目的がはっきりしていれば、必要な情報や着目点も明確になります。
2. 情報収集を行う
次に、実際のユーザーに関するデータを収集します。理想や想像だけでは、信頼性のあるペルソナは作れません。実在する顧客から得られた「事実」に基づく設計が重要です。
具体的には、ユーザーインタビュー、アンケート、アクセス解析、SNSの反応などが有効です。収集する項目は、属性情報だけでなく、趣味嗜好、価値観、悩み、よく使うメディアなど幅広くカバーすることがポイントです。
3. 共通項を抽出する
集めた情報から、複数のユーザーに共通する特徴や行動パターンを整理します。たとえば「スマホで買い物をする」「夜22時以降にSNSを利用する」など、具体的な行動の共通点を探ります。
この作業を行うことで、架空の人物像にリアリティが生まれ、実際のマーケティング施策にも活かしやすくなります。
4. 人物像を具体化する
ここでは、ペルソナを1人の“人”として具体化します。名前・年齢・性別・職業・年収・家族構成・趣味・悩み・よく見るメディアなどを細かく設定し、物語性を持たせることで、より生きた人物像が出来上がります。
たとえば、「佐藤未来さん(35歳・東京都在住・中堅出版社勤務・未婚)…」といった形で、文章でペルソナ紹介文を作成するのも有効です。
5. 社内共有と見直しを行う
完成したペルソナは、プロジェクト関係者全員と共有し、認識を合わせましょう。その上で、施策を進める中で新しい情報やズレが出てきた場合は、都度見直すことが重要です。
ペルソナは一度作ったら終わりではなく、継続的に更新・改善していく必要があります。
情報収集に使える主な方法とツール
インタビュー(顧客や社内営業担当へのヒアリング)
顧客との1対1のインタビューは、ユーザーの「なぜ」に迫るのに最適な手段です。課題や不安、製品に対する期待など、表には出ない深層心理まで把握できます。
また、社内の営業やサポート担当も貴重な情報源です。実際のやり取りの中で得た「生の声」を共有してもらうことで、リアルなユーザー像を掴むことができます。
アンケート(Webフォームなどを活用)
インタビューに比べて大規模に調査できるのがアンケートです。GoogleフォームやSurveyMonkeyなどのツールを活用すれば、無料でも十分な設問設計が可能です。
定量的なデータを得られるため、どの属性のユーザーがどのような傾向を持っているのか、傾向分析に向いています。
Googleアナリティクス・SNS分析(ユーザー行動の定量データ)
Webサイトへのアクセス解析やSNSでのエンゲージメントは、ユーザー行動を客観的に分析するうえで有効です。たとえば、滞在時間や離脱率からユーザーの興味関心を把握し、ペルソナの行動傾向として取り入れることができます。
ユーザーレビューや口コミ分析
Amazonレビュー、価格.com、SNSなどのユーザーレビューも重要な情報源です。ユーザーがどんな言葉で商品を評価しているかを知ることで、ペルソナの語彙や価値観を反映しやすくなります。
ペルソナ設計の手順
ペルソナ設計には一定のプロセスがあります。ここでは5つの基本ステップと、情報収集に役立つ具体的な方法やツールについて解説します。初心者でも順を追って進めることで、質の高いペルソナ設計が可能になります。
ペルソナ設計の基本ステップ
1. 目的を明確にする
最初のステップは、ペルソナ設計の目的をはっきりさせることです。
自社の商品・サービスにおいて「誰の課題を解決したいのか」「どのチャネルに活用するのか」といった目的が曖昧だと、的外れなペルソナになりかねません。
たとえば、ECサイトの購入率を上げたい場合と、オウンドメディアの読者数を増やしたい場合では、設計すべきペルソナの焦点が変わってきます。
目的がはっきりしていれば、必要な情報や着目点も明確になります。
2. 情報収集を行う
次に、実際のユーザーに関するデータを収集します。理想や想像だけでは、信頼性のあるペルソナは作れません。
実在する顧客から得られた「事実」に基づく設計が重要です。
具体的には、ユーザーインタビュー、アンケート、アクセス解析、SNSの反応などが有効です。
収集する項目は、属性情報だけでなく、趣味嗜好、価値観、悩み、よく使うメディアなど幅広くカバーすることがポイントです。
3. 共通項を抽出する
集めた情報から、複数のユーザーに共通する特徴や行動パターンを整理します。
たとえば「スマホで買い物をする」「夜22時以降にSNSを利用する」など、具体的な行動の共通点を探ります。
この作業を行うことで、架空の人物像にリアリティが生まれ、実際のマーケティング施策にも活かしやすくなります。
4. 人物像を具体化する
ここでは、ペルソナを1人の“人”として具体化します。名前・年齢・性別・職業・年収・家族構成・趣味・悩み・よく見るメディアなどを細かく設定し、物語性を持たせることで、より生きた人物像が出来上がります。
たとえば、「佐藤未来さん(35歳・東京都在住・中堅出版社勤務・未婚)…」といった形で、文章でペルソナ紹介文を作成するのも有効です。
5. 社内共有と見直しを行う
完成したペルソナは、プロジェクト関係者全員と共有し、認識を合わせましょう。その上で、施策を進める中で新しい情報やズレが出てきた場合は、都度見直すことが重要です。
ペルソナは一度作ったら終わりではなく、継続的に更新・改善していく必要があります。
情報収集に使える主な方法とツール
インタビュー(顧客や社内営業担当へのヒアリング)
顧客との1対1のインタビューは、ユーザーの「なぜ」に迫るのに最適な手段です。課題や不安、製品に対する期待など、表には出ない深層心理まで把握できます。
また、社内の営業やサポート担当も貴重な情報源です。実際のやり取りの中で得た「生の声」を共有してもらうことで、リアルなユーザー像を掴むことができます。
アンケート(Webフォームなどを活用)
インタビューに比べて大規模に調査できるのがアンケートです。GoogleフォームやSurveyMonkeyなどのツールを活用すれば、無料でも十分な設問設計が可能です。
定量的なデータを得られるため、どの属性のユーザーがどのような傾向を持っているのか、傾向分析に向いています。
Googleアナリティクス・SNS分析(ユーザー行動の定量データ)
Webサイトへのアクセス解析やSNSでのエンゲージメントは、ユーザー行動を客観的に分析するうえで有効です。
たとえば、滞在時間や離脱率からユーザーの興味関心を把握し、ペルソナの行動傾向として取り入れることができます。
ユーザーレビューや口コミ分析
Amazonレビュー、価格.com、SNSなどのユーザーレビューも重要な情報源です。
ユーザーがどんな言葉で商品を評価しているかを知ることで、ペルソナの語彙や価値観を反映しやすくなります。
ペルソナ設計で集客を成功させるためのポイント
ペルソナ設計は、単に「想像でつくる人物像」ではなく、実際のマーケティング施策を成功に導くための戦略的なツールです。
このセクションでは、精度の高いペルソナを設計するためのポイントや注意点、BtoBとBtoCそれぞれで異なるアプローチについて解説します。
実在の人物に基づく設計をする
ペルソナは、想像だけでつくると現実離れしたものになり、実際のマーケティング施策に活かしづらくなります。
そこで重要なのが、「実在の顧客や見込み顧客」のデータに基づいて設計することです。
たとえば、すでに購入実績のあるユーザーの中からロイヤルカスタマーをピックアップし、その行動や嗜好、ライフスタイルを詳細に分析することで、説得力のあるペルソナが完成します。
また、SNSやメールの問い合わせなど、日常的なコミュニケーションからもヒントが得られます。
マーケターの主観を排除する
マーケティング担当者自身の「こうあるべき」「自分ならこう思う」といった主観を反映させすぎると、実際のユーザー像とズレが生じる可能性があります。
特に注意したいのは、自社やブランドへの思い入れが強い場合です。
主観を避けるためには、ユーザーの声や行動データを客観的に分析すること、チームメンバーや外部関係者の視点を取り入れることが大切です。
複数人で検討することで、思い込みや偏見を排除しやすくなります。
チームで共有・ブラッシュアップする
ペルソナはチームで共有し、定期的にブラッシュアップすることが大切です。
プロジェクトが進む中で得られた新しい情報をもとに更新したり、成果に応じて調整したりすることで、常に実態に近いペルソナを維持できます。
また、営業・CS・商品開発など各部署とも連携し、意見を取り入れることで、多面的な視点からリアリティのあるペルソナが作られます。
定例ミーティング等でペルソナを再確認する場を設けるのも効果的です。
BtoB・BtoCでのペルソナ設計の違い
ペルソナ設計のアプローチは、BtoB(法人向け)とBtoC(個人向け)で異なります。
それぞれの特性に応じたポイントを押さえる必要があります。
BtoB:企業属性・役職・導入背景・意思決定プロセスなどを含めて設計
BtoBでは、個人ではなく「企業」との関係性がベースになります。
そのため、以下のような情報をペルソナに含めると効果的です。
- 企業規模(中小企業、大企業など)
- 業種(IT、不動産、製造業など)
- 担当者の役職(課長、部長、経営者など)
- 製品導入の背景(業務改善、コスト削減など)
- 意思決定のプロセス(稟議制か、経営判断か)
BtoBでは1人の判断だけで購買に至らない場合も多いため、「意思決定フロー」や「インフルエンサーの存在」までを視野に入れた設計が重要です。
BtoC:ライフスタイル・価値観・感情的な動機に着目
BtoCでは、ユーザーの個人の生活や感情が購入判断に直結します。そのため、以下のような視点が求められます。
- 日常の行動パターン(通勤、週末の過ごし方など)
- 使用しているSNSやアプリ
- 興味関心、趣味
- 購入のきっかけや動機(安心感、憧れ、コンプレックス解消など)
「自分が使う姿をイメージできるかどうか」が重要になるため、共感を呼ぶようなペルソナ設計が効果を発揮します。
すぐに使えるペルソナ設計テンプレート
ペルソナ設計を行う際に、「何をどこまで書けばよいのか分からない」という声をよく聞きます。
そこでこのセクションでは、すぐに実務で使えるペルソナ設計のテンプレートと、その記入方法について詳しく解説します。
BtoB・BtoC両方に対応できる構成にしているため、自社のビジネスに合わせてカスタマイズしてご活用ください。
ペルソナテンプレートの基本構成
以下は、一般的なペルソナ設計に用いられる項目を一覧にまとめたテンプレートです。
| 項目 | 内容 | 補足ポイント |
|------|------|--------------|
| 名前 | 例:田中 花子 | 実在しそうな日本人名を設定 |
| 年齢・性別 | 例:32歳・女性 | 購買判断に影響を与える年齢層を想定 |
| 居住地 | 例:東京都杉並区 | 地域特性に応じたニーズを想定 |
| 職業・年収 | 例:営業職・年収480万円 | ライフスタイルや支出傾向を反映 |
| 家族構成 | 例:夫と2人暮らし | 生活環境による価値観の違いに配慮 |
| 趣味・関心 | 例:カフェ巡り、SNS、旅行 | 消費行動や情報収集源の参考に |
| 課題・悩み | 例:仕事が忙しく、買い物の時間がない | 商品・サービスが解決できる課題を明確に |
| 情報収集源 | 例:Instagram、YouTube、口コミ | アプローチすべきチャネルの参考に |
| 購買の決め手 | 例:時短できるか、コスパが良いか | 実際の訴求ポイントに直結 |
| ブランドとの接点 | 例:Instagram広告で知った | タッチポイントの最適化に活用 |
このテンプレートをもとに、自社のターゲットに近い既存顧客や見込み顧客の情報を整理し、実在感のあるペルソナを設計します。
テンプレート活用のポイント
テンプレートを活用する際のポイントは、「できるだけ具体的に記入すること」と「チームでレビューすること」です。
たとえば、「SNSをよく使う」と記載するよりも、「Instagramを毎日20分以上チェックし、好きなインフルエンサーの投稿から商品を購入することが多い」と書いたほうが、訴求ポイントが明確になります。
また、作成後は必ずチームで共有し、各部門の視点を取り入れて内容をブラッシュアップしましょう。
営業チームが「実際はもっと価格に敏感だ」といった現場感覚を持っていることも多く、実践的な内容にするうえで非常に重要です。
まとめ
ペルソナ設計は、マーケティングや商品開発、コンテンツ戦略など、あらゆるビジネス施策の出発点となる重要な工程です。
本記事では、「ペルソナ設計とは何か?」という基本的な疑問から、設計の目的、手順、実務での活用方法までを詳しく解説しました。
ペルソナをしっかりと設計することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- ユーザー理解が深まり、ニーズに即した施策が可能になる
- マーケティングや制作の方向性に一貫性が生まれる
- 社内やクライアントとの認識のズレを減らし、円滑なプロジェクト進行ができる
ペルソナ設計においては、主観を排除し、実際のデータやユーザーの声をベースに構築することが重要です。
BtoBとBtoCで異なる視点を取り入れつつ、現場からのフィードバックを活かして継続的に見直し、精度を高めていくことが成功の鍵となります。
最後に紹介したテンプレートも活用しながら、まずは小さな施策からでもペルソナ設計を取り入れてみてください。
きっと、ユーザーの反応や成果に変化を感じられるはずです。
今後のマーケティング施策において、より実践的で効果的なペルソナ設計が皆様の成果向上に繋がることを願っています。