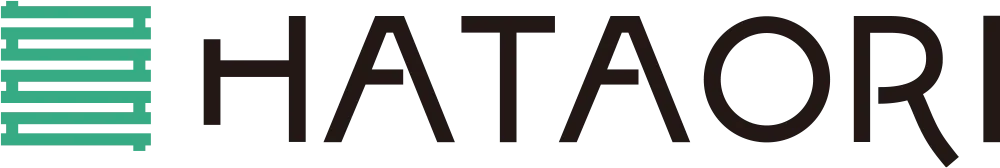なぜホームページを制作する?制作の目的とサイトに秘めた力について解説
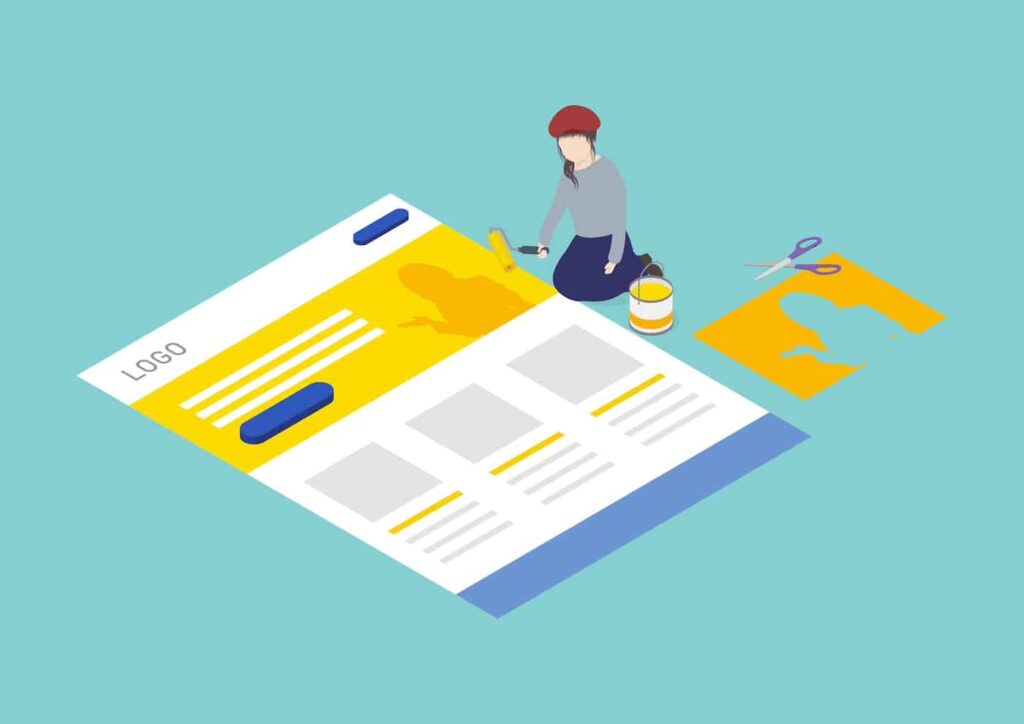
ホームページで「何ができるのか」「どんな目的で作るべきか」「費用や制作期間の目安はどのくらいか」など、悩みや疑問を明確に解決できる構成です。
初めて制作を検討する方にもわかりやすく、段階的に理解できる内容となっています。
「ホームページを作るべきかどうか迷っている」「SNSがあれば十分では?」と考える企業担当者は少なくありません。
しかし、ホームページは単なる情報発信の場ではなく、企業の信頼性を高め、ビジネスチャンスを広げる重要なツールです。
本記事では、ホームページ制作の目的や効果、制作にかかる費用や時間について、具体的な事例を交えて解説します。
目次
ホームページを制作する目的とは
ホームページはなぜ必要なのでしょうか?ここでは、企業がホームページを制作する背景や理由、そして持たないことによるリスクについて解説します。
単なる「作った方がいい」ではなく、「なぜ必要か」が明確になります。
なぜ今、企業にホームページが必要か
現代では、消費者や取引先が企業情報をインターネットで検索するのが一般的です。
ホームページがない企業は存在しないかのように見なされることもあります。
また、法人口座の開設や補助金申請時に、ホームページの提示を求められるケースも増えています。
つまり、ホームページは企業の「顔」として、信頼性を示す重要な役割を担っています。
ホームページがない場合のデメリット
ホームページがないと以下のようなデメリットが考えられます。
- 信頼性の欠如:取引先や顧客からの信頼を得にくい。
- 情報発信の制限:最新情報やサービス内容を効果的に伝えられない。
- ビジネスチャンスの損失:オンラインでの問い合わせや受注の機会を逃す。
これらのデメリットは、企業の成長や発展を妨げる要因となり得ます。
SNSとの違いとホームページの独自価値
SNSは情報拡散力に優れていますが、投稿が流れてしまい必要な情報にすぐアクセスできないことがあります。
一方、ホームページは情報を整理して掲載でき、訪問者が必要な情報を容易に見つけられます。
また、SNSはプラットフォームの仕様変更やアカウント停止のリスクがありますがホームページは自社で管理できるため、安定した情報発信が可能です。
ホームページで実現できることとは
ホームページは情報を発信するだけの場ではありません。
業務効率化や売上拡大、採用強化など、さまざまな目的に応じて機能を持たせることができます。
具体的にどのような活用ができるのかを見ていきましょう。
情報発信・問い合わせ・予約機能の活用
ホームページでは、企業情報やサービス内容を詳細に掲載できます。
また、問い合わせフォームや予約システムを設置することで、顧客との接点を増やし業務効率化にもつながります。
たとえば、飲食店がオンライン予約システムを導入することで電話対応の手間を減らし予約管理をスムーズに行えるようになります。
EC・採用・顧客サポートなどの応用
ホームページにEC機能を追加すれば、オンラインでの商品販売が可能になります。
また、採用情報を掲載し、応募フォームを設置することで採用活動を効率化できます。 さらに、FAQやチャットボットを導入することで、顧客サポートの質を向上させることも可能です。
名刺代わりにとどまらない価値
創業期の企業にとって、ホームページは「名刺代わり」としての役割が大きいですがそれ以上の価値があります。
たとえば、銀行口座の開設や融資、補助金申請時に、ホームページが企業の信頼性を示す資料として活用されることがあります。
また、取引先が企業情報を事前に確認できるため、商談のスムーズな進行にも寄与します。
目的を明確にすることの重要性
ホームページは「何となく」作っても効果が出にくいものです。 どんな成果を得たいのか、明確な目的を持つことで必要な機能やデザインの方向性が決まります。
ここでは目的設定の重要性について解説します。
ホームページは目的次第で効果が変わる
ホームページの効果は目的によって大きく変わります。
たとえば、集客を目的とする場合は、SEO対策や広告運用が重要になります。
一方、採用を目的とする場合は、企業文化や働く環境を伝えるコンテンツが求められます。
目的を明確にすることで、必要な機能やコンテンツが明確になり効果的なホームページ制作が可能になります。
よくある目的別の分類と事例紹介
企業によってホームページを作る目的はさまざまです。
ここでは目的ごとに分類された具体的な事例を紹介しながら自社のホームページ制作の参考になるヒントを提供します。
自社にとっての目的の見つけ方
ホームページの目的を見つけるには自社の課題や目標を洗い出し、それを解決・達成するためにホームページがどのように役立つかを考えることが重要です。
たとえば、新規顧客の獲得が課題であれば集客を目的としたホームページが必要になります。
認知度向上
地域密着型の小売店が地元の人々に自店を知ってもらうためにホームページを制作し、店舗情報やイベント情報を発信することで認知度を高めることができます。
集客・リード獲得
美容院がホームページに施術メニューや料金、スタッフ紹介を掲載し、オンライン予約機能を導入することで新規顧客の獲得につなげることができます。
採用活動
IT企業がホームページに採用情報や社員インタビュー、福利厚生の紹介を掲載することで求職者に企業の魅力を伝え応募を促進できます。
ブランディング
高級レストランが洗練されたデザインのホームページを制作し、料理や内装の写真を掲載することでブランドイメージを強化できます。
顧客サポート
家電メーカーが、ホームページに製品の取扱説明書やFAQ、問い合わせフォームを設置することで顧客の疑問や問題を迅速に解決できます。
ターゲットと目的の関係性を考える
ホームページ制作で忘れてはならないのが、「誰に向けて作るか」という視点です。
届けたい相手に合った設計ができていなければ、どれだけ立派なサイトでも成果は出ません。
ここではターゲットと目的をどう結びつけるかを解説します。
「誰に何を届けたいか」が設計の出発点
ホームページ制作では、ターゲットとなる顧客像を明確にすることが重要です。
たとえば、若年層をターゲットとする場合は、スマートフォンでの閲覧を意識したデザインやSNSとの連携が効果的です。
ターゲットに合わせたコンテンツや機能を設計することで、目的達成に近づけます。
ペルソナ設計と目的の整合性の取り方
ペルソナとは、ターゲット顧客の具体的な人物像を設定する手法です。
たとえば30代女性で美容に関心が高い主婦をペルソナとした場合、ホームページには美容情報やお得なキャンペーン情報を掲載することで関心を引きやすくなります。
目的とペルソナを一致させることで、効果的なホームページが実現します。
ホームページがもたらす主な効果
目的に応じたホームページを制作することで、企業には多くのメリットがもたらされます。
ここでは、具体的な効果として信頼性の向上や業務効率化、問い合わせの増加などを詳しく紹介します。
信頼性の向上と企業イメージの形成
ホームページを持つことで、企業の信頼性が高まり取引先や顧客からの評価が向上します。
また、デザインやコンテンツによって、企業のイメージを形成しブランド価値を高めることができます。
営業効率や業務効率の改善
ホームページに製品情報やFAQを掲載することで、営業担当者が説明する手間を省けます。
1また、問い合わせフォームやオンライン予約システムを導入することで業務の効率化が図れます。
ホームページ制作の基本的な流れ
ホームページを作るには、いきなり制作会社に依頼するのではなく、事前準備から公開後の運用まで一連のプロセスを理解することが重要です。
ここでは、制作前の計画段階から実制作、公開、そして運用・改善までの基本的な流れについて解説します。
制作前に準備すべきこと
ホームページ制作において最も大切なのが「事前準備」です。
目的やターゲットを明確にすることで、ブレのないサイト設計が可能になります。
たとえば、「新規顧客を増やしたい」のか「採用活動を強化したい」のかで、サイト構成やデザインの方向性は大きく異なります。
まずは以下のような点を整理しましょう。
- ホームページの目的(例:集客、採用、情報発信)
- ターゲットとなるユーザー像(年齢・性別・職業など)
- 掲載するコンテンツ(会社概要、サービス紹介、お知らせなど)
- 必要な機能(お問い合わせフォーム、カレンダー、EC機能など)
これらを明確にした上で、必要に応じて社内で情報をまとめた企画書を作成すると外部パートナーとのやりとりもスムーズに進められます。
制作会社とのやりとりのポイント
制作を外注する場合、パートナー選びも非常に重要です。 単にデザインがきれいというだけでなく自社の意図を汲み取り、成果に結びつける提案ができるかどうかを見極めましょう。 打ち合わせの際は、「目的」「ターゲット」「コンテンツの構成」などを具体的に伝えるとミスマッチを防ぐことができます。 また、以下のポイントを事前に共有しておくと安心です。
- 予算と納期
- 競合となる他社サイト
- 好みのデザインや色使い
- 社内での確認フロー(誰がチェックするか)
円滑なコミュニケーションのために、メールだけでなく定期的なオンラインミーティングも取り入れるのがおすすめです。
公開後の運用と改善の重要性
ホームページは「作って終わり」ではありません。
むしろ、公開後の運用・改善こそが成果に直結するフェーズです。
たとえば、ブログ記事を更新して検索流入を増やしたり、アクセス解析ツール(Googleアナリティクスなど)で訪問者の動向をチェックし、改善策を講じたりといった活動が必要になります。
また、新しいサービス開始や人事異動、営業時間の変更といった社内情報もタイムリーに反映することで信頼性を維持できます。
運用体制を社内で整備するか、外部に保守管理を委託するかは、サイト規模や社内リソースに応じて検討しましょう。
ホームページ制作にかかる費用の目安
ホームページ制作にはどのくらいの費用がかかるのか、多くの方が気になるポイントではないでしょうか。
費用は目的や機能、依頼先の種類によって大きく変わります。
ここでは制作費の相場と構成要素、安価なサービスの特徴や注意点、自社に合った費用感の見極め方について解説します。
制作費の相場と費用構成の内訳
一般的な中小企業のコーポレートサイト(5~10ページ程度)の場合、制作費の相場は30万〜100万円程度とされています。
ただし、ページ数が多い、特別なシステム開発が必要、デザインに強いこだわりがあるといったケースでは100万円を超えることも珍しくありません。
費用の内訳としては、以下のような項目が含まれることが一般的です。
| 費用項目 | 内容例 |
|---|---|
| 企画・設計費 | サイト構成の設計、ワイヤーフレームの作成など |
| デザイン費 | トップページ・下層ページのビジュアル制作 |
| コーディング費 | HTML/CSS/JavaScriptなどでの実装 |
| CMS構築費 | WordPressなどのシステム設定・導入 |
| 原稿作成費 | 文章の執筆、コピーライティング |
| 撮影・素材費 | 写真・動画の撮影、画像購入など |
| 保守・管理費 | 公開後の修正対応やシステムの更新など(月額契約) |
このように単なるデザインだけでなく、設計・執筆・システム構築までを含めた包括的なサービスであるため、見積もりを比較する際は「何が含まれているか」を必ず確認しましょう。
安価な制作サービスの特徴と注意点
最近では、10万円以下で制作できる格安サービスや月額制のテンプレート型サービスも登場しています。
これらは初期費用を抑えられる一方で、自由度やサポート体制に制限がある場合もあります。 たとえば、以下のような点に注意が必要です。
- デザインがテンプレートで他社と似通ってしまう
- 独自機能やカスタマイズがしにくい
- 月額費用が高く、長期的に見ると割高になることもある
- データが外部管理のため、サイトの引っ越しが難しい
コストを抑えたい気持ちは当然ですが、長く使うホームページであることを考えると「初期費用だけ」で安易に判断してはいけません。
数年単位の運用やデザイン力などを総合的に想定したうえで、選択することが得策です。
自社に合った費用感を見極める方法
予算を組む際は「費用対効果」を意識することが大切です。
たとえば、新規顧客を月5人獲得できるサイトであれば、年間で60人の見込み顧客を得られる計算になります。
そこから受注に結びつく率や平均単価を想定すれば、制作費の回収時期を具体的にシミュレーションできます。
また、「目的」と「規模感」に応じて段階的に投資する方法も有効です。
最初は情報発信のみのシンプルな構成で公開し、反応を見ながらページや機能を追加していく、といった段階的な制作も視野に入れて検討してみてください。
制作にかかる時間とスケジュール感
ホームページ制作には想像以上に時間がかかることもあります。 余裕を持ったスケジュール設計が重要です。
ここでは、一般的な制作期間の目安や各フェーズの作業内容、スケジュール遅延を防ぐための工夫について解説します。
一般的な制作期間の目安
中小企業向けの標準的なコーポレートサイト(5~10ページ程度)であれば、企画から公開までに2〜3ヶ月程度を見込んでおくのが一般的です。
ただし、掲載内容が多かったり、オリジナル機能の開発が必要だったりする場合は3ヶ月以上かかることもあります。
以下はよくあるスケジュールの例です。
| フェーズ 期間(目安) | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 1. 企画・要件定義 | 1〜2週間 | 目的の確認、ターゲット設定、構成案作成など |
| 2. 設計・構成 | 1〜2週間 | サイトマップ作成、ワイヤーフレーム設計 |
| 3. デザイン制作 | 2〜3週間 | トップページ・下層ページのビジュアル作成 |
| 4. 実装・構築 | 3〜4週間 | HTML/CSS/JavaScriptのコーディング、CMS構築など |
| 5. 最終調整・公開 | 1週間程度 | 動作確認、修正対応、サーバーへのアップロードなど |
これに加え、社内確認や素材提供の遅れがあると、さらに時間が延びることもあります。
スケジュールを遅らせないためのコツ
ホームページ制作が予定より長引く最大の要因は、情報提供の遅れと社内での確認フローの停滞です。
特に以下のような対応を事前に整備しておくと、スムーズに進行できます。
- 写真・文章などの素材を事前に準備しておく
- 社内の確認担当者を決めておく(できれば1名に集約)
- 修正依頼は一括でまとめて伝える
- 打ち合わせ日程をあらかじめ設定しておく
また、制作会社からの提案に対して「とりあえず保留」「検討中です」といった対応が続くと全体のスケジュールがずれ込んでしまいます。
可能な限り、スピーディーな意思決定を心がけましょう。
ホームページ制作に失敗しないためのポイント
ホームページ制作は一度公開すれば終わりというものではありません。
中長期的に活用できるものにするためには、制作段階から押さえておきたい重要なポイントがあります。
ここでは、よくある失敗例とその対策、成功に導くためのチェックリストについて解説します。
よくある失敗とその原因
ホームページ制作でよくある失敗の一つは、目的があいまいなまま制作を進めてしまうことです。
たとえば「とりあえず名刺代わりに」と考えて作ると、誰に向けたサイトか分かりにくく結果的に訪問者に響かない内容になってしまうことがあります。
また、見た目のデザインに偏りすぎるのも落とし穴のひとつです。 ビジュアルはもちろん大切ですが、情報の伝わりやすさや使いやすさも同じくらい重要です。
たとえば、必要な情報にたどり着くまでにクリックが何回も必要なサイトはユーザーの離脱を招いてしまいます。
さらに、公開後の更新を怠ってしまうケースも少なくありません。
せっかく制作しても、1年以上更新が止まっていると「この会社はちゃんと活動しているのか?」といった不安を与えてしまいます。
成功させるためのチェックリスト
失敗を避け、成果につながるホームページを作るには以下の点を意識することが大切です。
| チェック項目 | 内容例 |
|---|---|
| 目的が明確になっているか | 認知拡大、問い合わせ獲得、採用強化など |
| ターゲットが設定されているか | 誰に向けて発信するのかを具体的に定める |
| 構成・導線が整理されているか | 情報が整理され、迷わず目的の行動ができる設計になっているか |
| 更新・運用の体制が整っているか | 社内で更新を担当する人やルールを決めているか |
| デザインとユーザビリティの両立 | 見やすさ・使いやすさとブランドイメージを両立できているか |
このように、制作前の準備段階での「考える力」と公開後の「育てる意識」が、成功するホームページの鍵を握っています。
ホームページは「会社の顔」である
ホームページは現代の企業にとって単なる情報掲載ツールではなく、会社の「顔」としての役割を担っています。
初対面の相手に名刺を渡すように、インターネット上ではホームページが企業の第一印象を決定づける存在です。
ここでは、その役割と重要性について詳しく解説します。
名刺代わり以上の役割と可能性
「ホームページは名刺代わり」とよく言われますが、実際にはそれ以上の機能と価値を持っています。
名刺は一方向的な情報の提示にすぎませんが、ホームページは双方向のコミュニケーションを可能にします。
たとえば、企業理念や代表メッセージを掲載することで、企業の信念や姿勢を訪問者に伝えることができます。
また、スタッフ紹介や導入事例、ブログなどを通じて会社の「中身」や「人となり」を発信することもできます。
さらに、お問い合わせフォームやチャット機能を設けることで、訪問者との直接的な接点も作ることができるのです。
これは名刺では決してできない大きな価値です。
オンライン上での信頼構築の重要性
人と人とのビジネスにおいて「信頼」は欠かせません。 そしてその信頼は、対面だけでなくオンラインでも築く必要があります。
現代では、商品やサービスを知った人がまず企業名を検索しホームページを訪問する流れが一般的です。
そのとき、情報が整理されていてデザインも整ったサイトであれば、「この会社はしっかりしている」という安心感を与えることができます。
逆に、更新が止まり、スマホに対応していない古いサイトであれば、せっかくの興味も一気に失われてしまいます。
つまり、ホームページはただ存在すれば良いのではなく、「今の自社を正しく、魅力的に伝える」ための設計と運用が求められるのです。
ホームページが「当たり前」の時代に
かつては、ホームページを持っている企業は「先進的」とされました。
しかし現在では、ホームページの存在自体が「持っていて当たり前」と見なされる時代になっています。
このような社会背景において、なぜ改めてホームページが必要なのか、その意味を考えてみましょう。
今の時代、スマホで「気になる会社」を検索し、その会社のホームページがすぐに表示されるかどうかは信頼性や企業力の判断材料になっています。
たとえば、新規の取引先候補が検索してもホームページが見つからない場合、「本当にこの会社は存在するのか?」「小規模で不安定なのでは?」といったネガティブな印象を持たれてしまうことも少なくありません。
また、SNSだけでは情報が流れてしまい、必要なときに必要な情報へたどり着きにくいという弱点もあります。
企業の公式な情報発信の基盤として、ホームページは引き続き不可欠な存在なのです。
HATAORIでは、神奈川県秦野市でも安価でサイト制作を承っております。
サイト制作を検討されている方や、サイト制作をしたいけど目的が曖昧な方などお気軽にご相談ください。
参考文献
- 中小企業のためのホームページ活用ガイド
- 経済産業省「IT導入補助金」活用事例集
- 日本ウェブデザイナーズ協会「企業ホームページ制作の基本」
- Web担当者Forum:ホームページ制作の基礎知識
- Webサイトの目的とは?曖昧な状態から脱却して成果を出すための考え方
- ホームページ制作の目的とは?効果を出すための考え方や流れを解説
- ホームページの役割と目的|企業のWebサイトは何のために存在するのか
- 【徹底解説】ホームページの役割とは?目的別にご紹介
- ホームページの費用相場は?内訳や料金別にできることを解説
- ホームページ作成にかかる期間はどのくらい?ホームページの種類別に解説
- 顧客管理の方法とは?基本からツールの選び方まで徹底解説 | 新規事業や組織の営業戦略/営業支援(コンサル)ならSALES ASSET